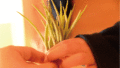「中古でも自然素材」って、わがままですか?
僕のところに相談に来てくれる人の中には、
こんなふうに前置きして話し始める方がよくいます。
「本当は無垢の床とか、漆喰の壁とか、すごく憧れるんですけど……
でも、中古だし、やっぱり贅沢かなって」
その言葉を聞くたびに、僕は心の中で静かに首を振ります。
いや、それは“わがまま”なんかじゃない。
むしろ、それは「本音」ですよね?
きれいな空気の中で暮らしたい。素足で気持ちいい床に寝転びたい。
建材の匂いがしない、呼吸できる壁のある家に住みたい。
中古住宅を選ばざるを得ない現実の中でも、
自分や家族にとって“まっとうな暮らし”を大事にしたい——
そう思うのは、まったく自然な感覚です。
でもたぶん、頭のどこかでこうも思ってる。
「新築でもないのに、そんな理想を言っていいのかな?」
「築30年の家で、素材にこだわるなんて変かな?」
僕はそういう“引け目のある理想”にこそ、応えたいと思ってます。
“中古”だからこそ、本物の素材が必要な理由
中古住宅って、確かに築年数や劣化は気になります。
断熱性能も不十分なことが多いし、間取りが今の暮らしに合ってないこともある。
だからこそ、素材の力を借りる価値がある。
- 杉や桧の床は、温熱環境の弱さをカバーしてくれる
- 漆喰や珪藻土は、古い家特有の空気の重さを整えてくれる
- 自然素材が“余白”を生むことで、住まい手が呼吸しやすくなる
つまり、「築古=理想をあきらめる」ではなく、
**“築古だからこそ、素材の本質が効く”**という視点もあるんです。
中古リノベ=“足りない中で選ぶ”ではない
中古リノベって、どこか“我慢”のイメージが強い。
間取りはある程度仕方ない。素材も諦めるしかない。完璧は望めない。
でも僕は、そのイメージをもう一段、超えていきたい。
「今あるものを活かしながら、ちゃんと“好き”を諦めない」
そんなリノベができたら、暮らしに対する自信が生まれるんじゃないかって。
▶ 次章へ
では、実際に「自然素材を使った中古リノベ」がどこまで可能なのか?
費用や構造の問題、そして“素材にとっての適性”を、次章ではリアルに掘り下げていきます。
「自然素材のリノベは高い」って本当?
「自然素材って高いですよね?」
これも、中古リノベを考える人がよく口にするフレーズです。
もちろん、無垢材や漆喰は、量産された建材よりはコストがかかります。
でも僕が現場で感じているのは、“できる/できない”を決めているのは予算そのものじゃないということ。
それより大きいのは、
「その家に、それが“合うかどうか”」という視点なんです。
素材が活きるかどうかは、構造と下地で決まる
たとえば、築30年の木造住宅をリノベする場合。
床下を覗くと、土台が湿気で傷んでいたり、シロアリの形跡があることがあります。
この状態のまま、無垢の杉板を張っても、数年後には反りや腐食のリスクが出てくる。
つまり、“素材を使う準備が整っているか”が大前提。
- 構造に大きなゆがみがあるか
- 床や壁の下地が再生可能なレベルか
- 湿気の逃げ道があるか、断熱材が機能するか
これらがクリアされて初めて、「素材を活かす選択肢」が見えてきます。
「費用をかけて素材を入れる」ではなく、「素材が費用を回収してくれる」こともある
たとえば断熱リノベを同時に行う場合。
窓の断熱性を高めて気密を調整すると、無垢材の温もりが格段に際立ちます。
逆に、断熱が甘い家で無垢材だけを張っても、
冷気で足が冷えたり、結露で板が痛むことも。
つまり、素材を入れる=オプションではなく、
性能と空気の流れとセットで考えたとき、“コスト以上の効果”を発揮するわけです。
実例|築35年の家で自然素材を活かせた理由
以前手がけた築35年の住宅では、断熱性能がほぼゼロの状態でした。
けれど、基礎と柱はしっかりしていた。土台の入れ替えも最小限で済んだ。
そこで、断熱改修を行い、1階床に杉の赤身材を採用。
壁には漆喰、天井は既存を活かしつつ和紙クロスで調整。
住まい手の方は「今まで住んだどの家より空気が澄んでいる」と言ってくれました。
このときのポイントは、**構造と空気の設計が整ったうえで、素材を“迎え入れた”**こと。
“素材に見合う舞台”を整えるのが、僕の仕事
自然素材は、ただ貼ればいいものじゃない。
僕がいつも意識しているのは、「素材が本来の力を出せる状態」をつくること。
それができていないまま、見た目のためだけに無垢材や漆喰を使っても、
結局は「高いのに持たない」と言われてしまう。
だから僕は、“できるかどうか”の判断を予算だけでせず、
家のコンディションを見極めて、「迎える器」を整えることから始めます。
▶ 次章へ
では実際に、**「築古だからこそ自然素材が活きた」**という実例を、
次章では空気・温熱・感情の観点からお話ししていきます。
築古の家にこそ、自然素材がフィットする理由
自然素材は、「新しくて整った家」にこそ似合うと思われがちです。
でも僕は逆に、築年数が経った家ほど、素材の力が活きると感じています。
なぜか?
それは、“素材が持つ揺らぎ”と“築古の空気感”が噛み合うから。
たとえば築40年の家。
床はフワフワしていて、壁はクロスが浮き、天井には年季がにじんでいる。
でもその空間には、「無機質じゃない、暮らしの匂い」が残っているんです。
この“人の痕跡”に、自然素材の揺らぎが呼応すると、
家が新しくなるのではなく、**「深くなる」**という現象が起こる。
「素材が家に染まる」感覚
以前、築38年の団地リノベを担当したときの話。
元々の家は、アルミの窓サッシと化粧合板に囲まれた、“ザ・昭和”的な空間でした。
そこで床を赤身の杉に張り替え、天井はベニヤをはがして構造現しに。
壁は既存のボードの上に左官で漆喰を塗った。
その結果、“リノベ後のきれいさ”ではなく、“空気の深み”が生まれたんです。
住まい手の方がこう言ってくれました。
「新しくなったというより、昔からこうだったみたい。すごく落ち着きます」
空気の“重さ”と“軽さ”は、素材と設計で変えられる
築古の家には、独特の空気の重さがあります。
押入れや水まわりの匂い、換気がうまくいかない閉塞感。
これを改善するには、単なる“換気量の確保”だけでは不十分で、
素材が空気にどう関わるかを設計する必要があります。
- 杉は湿気を吸って呼吸する
- 漆喰や珪藻土は、空気中のニオイを吸着して調湿する
- 柿渋や和紙も、質感と湿度のバランスを整えてくれる
こうした**“空気に働きかける素材”**を組み合わせることで、
築古でも“深呼吸したくなる家”が生まれる。
僕が大切にしている問い
築年数に対して、「この家、まだいけるかな?」と聞かれることがあります。
そのとき僕は、耐震や構造はもちろんチェックするけれど、
それと同じくらいこう自問します。
「この家は、もう一度“いい空気”を取り戻せるか?」
素材は、単なる装飾じゃない。
空気の質を“再設計”するための道具なんです。
▶ 次章へ
では実際に、そうした自然素材リノベを経て、
住まい手が「やってよかった」と語ってくれた理由には、どんな共通点があるのか。
次章では、**施工後のリアルな感想から見えてきた“満足の構造”**を紐解いていきます。
「やってよかった」と言われる理由は、仕上がりの綺麗さじゃない
正直に言えば、僕のリノベ現場は、
SNSでバズるような“モデルルームっぽさ”はあまりない。
無垢材には節もムラもあるし、漆喰の壁も完璧には塗り込まない。
でも、住み始めて半年、1年が経った頃、住まい手からこう言われることがある。
「この家にして、本当に良かったと思ってます」
「なんか、“自分の家”って感じがするんです」
その言葉の背景には、見た目を超えた「居心地の納得」がある。
共通点①|“素材が落ち着く”空気感を持っている
自然素材を選ぶ理由は、「体にいい」だけじゃない。
むしろ住み手が最初に感じるのは、**空気の“やわらかさ”**です。
- 朝起きたとき、目がシパシパしない
- 冬でも床が冷たすぎない
- 帰宅時のニオイのこもりがほとんどない
「何が違うか分からないけど、空気が違う」
——これが最も多く聞くフレーズで、素材の効果がちゃんと“感覚”に届いている証です。
共通点②|“気を使わない”暮らしができている
これは、無垢の床や漆喰の壁だからこそ言えることですが、
最初は「汚れそう」「傷つきそう」と心配していた人ほど、後からラクになる。
- 子どもが裸足で暴れても、むしろそれが「うちらしさ」に感じる
- 傷も汚れも、“育っていく家の記録”として受け止められるようになる
- 「ちゃんと使ってる感」が心地いい
これは、「手間がかかるけど負担じゃない」
という感情と素材との共存状態なんだと思います。
共通点③|“設計の過程”が納得につながっている
素材の良さや動線の工夫よりも、
最終的に「満足」を決定づけるのは、一緒に考えたプロセスです。
- 間取りを決めるとき、「朝、ここに光が入るかどうか」を一緒に確認した
- 予算とのバランスを、“どこにかけて、どこを削るか”で本音で話した
- 「こうしたほうが素敵だけど、あなたの暮らしにはこっちが合う」と伝えてくれた
こういった“決断の共同体験”が、
住み始めたあとも、「納得した家」として根を張ってくれる。
「満足」は、コストじゃなく“解像度”で決まる
リノベって、選択肢が多いからこそ迷いやすい。
でも、「どこにこだわり、どこを委ねるか」が整理されていれば、
結果が予算以上の価値になることもある。
自然素材の家が満足されやすいのは、素材の力だけじゃなく、
それを“選び取るプロセス”ごと愛着になるから。
▶ 次章へ
では、そんなリノベの裏側で、
僕が実際にどんなことを見て、どこに注意しているのか?
次章では、**僕がリノベ前に“必ずチェックしている3つの視点”**をお話しします。
プロとして、必ずチェックする3つのこと
中古住宅のリノベは、「すでにあるもの」に手を入れる仕事です。
だからこそ、「見えないところ」にどれだけ目を向けられるかで、
完成後の満足度がまるで変ってきます。
僕が現場に入ったとき、まず見るのは間取りでも仕上げでもありません。
次の3つの視点を、徹底的に確認しています。
① 構造と基礎|この家は“育てる器”として耐えうるか
自然素材を使いたいなら、その土台がしっかりしていないと始まりません。
たとえば:
- 基礎にクラックが入っていないか
- 土台が腐っていないか(特に床下の通気と湿気)
- 筋交いや構造壁のバランスがとれているか
- 雨漏りの形跡、屋根や軒の状態
これをおろそかにして、無垢材や漆喰だけ入れても、数年後に不具合が出ます。
素材を「飾り」で終わらせないために、“器の健全性”を最初に確かめる。
② 空気と湿気の流れ|この家に“深呼吸できる余地”があるか
築古の家で多いのが、**「空気が抜けない家」**です。
風が通らない、水まわりがジメジメしている、結露が起きている——
これらは住み心地だけでなく、素材の寿命にも関わる問題です。
僕は現地調査でこういうことを見ます:
- 窓や開口部の配置と通風経路
- 床下換気の状態
- 北側の湿気たまり、壁体内の通気性
- サッシの種類と劣化状況
これらを押さえることで、**“換気扇だけじゃどうにもならない問題”**を見逃さないようにしています。
③ リノベによって“暮らしが変えられる余地”があるか
これは少し感覚的な視点です。
僕は家を見たときに、こう自問します。
「この家は、住む人の暮らし方を変える可能性があるか?」
「素材が入ることで、空気感が“更新”されるだろうか?」
たとえば:
- 玄関の抜け感を変えられるか
- 間仕切りを開放できるか
- 外と中のつながりを生かせるか
ただ「古いものを直す」のではなく、
“新しい暮らしを受け入れる構造かどうか”を見極めるようにしています。
僕の仕事は、素材を選ぶ前に「選ぶべき器を見極める」こと
どんなにいい素材でも、土台が整っていないと活きない。
換気が悪ければ、漆喰も腐りやすくなる。
構造が応えてくれないと、空間は萎縮する。
だから僕は、中古住宅を見るときに“希望”より先に“地盤”を見ます。
それは、「夢を叶えるための現実チェック」でもあるからです。
▶ 次章へ
ここまで読んできて、
「中古でも、自然素材っていけるんだな」と思ってくれた方がいたら、
僕はとても嬉しいです。
では最後に、**中古住宅リノベを考えるすべての人に伝えたい“根っこにある問い”**を、
締めの言葉としてお届けしたいと思います。
「中古リノベだから仕方ない」は、本当?
「間取りは妥協した」
「素材は諦めた」
「新築と比べたらね…」
——そうやって、どこか自分に“言い聞かせるように”住まいを語る人を、僕は何人も見てきました。
でも本当に、中古リノベって「妥協の選択肢」なんでしょうか?
僕はそうは思いません。
むしろ、「今あるものに手を入れて、好きな暮らしに近づけていく」
という行為こそ、住まいに対する成熟した愛情表現だと思っています。
そしてそのためには、“我慢しないで選ぶ”という感覚が必要です。
「ない中で選ぶ」から「ある中で育てる」へ
確かに、新築のようにすべてが自由ではありません。
制限もあるし、劣化もある。
でもその中で、
- 床に無垢の杉を選ぶこと
- 漆喰の壁で空気を整えること
- 使い込むほど味わいが出る素材を迎えること
それらは、“自分たちの暮らしを大切にしたい”という意思の現れだと思うんです。
僕の仕事は、その想いに“現実的な方法”を添えること。
「やりたいけど、やっぱり難しいですよね…?」と迷う人に、
「できますよ。ただ、こうやればもっと活きます」と答えること。
自然素材は、ただの建材じゃありません。
その人の“暮らしの哲学”を支える道具です。
僕が届けたいのは、「誇れる家」
新築じゃなくてもいい。
完璧じゃなくてもいい。
でも、「自分たちで考えて、選び取った」と胸を張れる家。
そんな住まいが、毎日の気持ちを少しだけ明るくしてくれる。
それが僕にとっての“誇れるリノベ”です。
最後に、問いかけを一つだけ
「今の暮らしに、ちょっとだけ“素直な理想”を足してみませんか?」
その一歩目が、
無垢の床でもいいし、自然素材の壁でもいいし、
「この家、好きかも」と言える気持ちでもいい。
僕は、その気持ちに全力で応える準備があります。