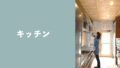京都で壁が湿る理由は断熱材と土壁の組み合わせだった
断熱材スタイロフォームとは
壁が湿っている気がする。
これは壁の中で結露が生じていることが多く、カビが大量に発生するなど、健康的にも問題があります。
しかし、そもそもなぜ壁の中で結露が発生するのでしょうか。
実は、壁の素材と断熱材の組み合わせが影響することがあるのです。
リノベーションで断熱性能を底上げしようとすると、まず名前が挙がるのが押出法ポリスチレンフォーム。いわゆるスタイロフォームです。
スタイロフォームの特徴は以下のとおりです。
・施工性が良い。
・熱抵抗値も高い。
・補助金の申請や性能等級の認定でも、計算上の数値が大きく伸びる。
このような理由から、今の改修現場ではごく当たり前のように採用されるようになりました。
しかし、ここで注意が必要なのは、断熱材と壁の素材の組み合わせです。
特に、京都の古民家に多い既存壁の「土壁」と組み合わさる時は要注意なのです。
京都の古民家に多い、土壁と現代の断熱材スタイロフォームの性質の違い
まずは材料の性格を整理してみましょう。
土壁は透湿性という性質を持っています。
これは、水蒸気を素材自体を通過することを言います。
つまり、土壁は湿気を吸ったり吐いたりすることができるのです。
それによって、調湿材として、夏は余分な湿気を抱え込み、冬は乾燥時に放出する。その働きによって室内の快適さが保たれる場面も多いのです。
一方、スタイロフォームは透湿抵抗が極めて高いのが特徴です。
糖質抵抗が高いと、水蒸気を表面で止めてしまいます。つまり、ほとんど水蒸気を通しません。
材料自体は水を吸わないため腐ることもありません。しかし、「湿気の流れを止める壁」になってしまうのです。
つまり、土壁とスタイロフォームは透湿の性格が真逆なんです。
土壁とスタイロフォームの断熱のセットで起きること
リノベーションでは、
室内側→ 石膏ボード → スタイロフォーム → 土壁 → 外壁通気層
という構造になっています。
この断面では、まず室内の湿気が石膏ボードを通過します。
ボードももちろん透湿抵抗はあります。しかし、防湿層と呼ばれる、「水蒸気を止める防波堤」が十分ではありません。こうなると、室内の水蒸気がコンセント穴や目地から抜けてしまいます。
そして、この次に現れるのがスタイロフォーム。
ここで透湿はほぼ遮断されるため、湿気はスタイロの室内側表面で止まります。
そして、温度条件によってはここで結露が発生してしまいます。
一部は隙間を伝って土壁に回り込みますが、既に出口が塞がれているので滞留しやすい状態です。
最後の外壁通気層。これは、雨水や外装の湿気を乾かすには効果的です。しかし、スタイロフォーム裏にたまった湿気を排出するには力が弱く、結露リスクを下げる役割はほとんど果たしません。
結果的に、スタイロフォームの表面から裏側にかけてが「見えない結露場」になりやすいのです。
土壁とスタイロフォーム組み合わせが選ばれる理由
では、どうして土壁とスタイロフォームの組み合わせが選ばれるのか。
理由は明確です。それは、補助金の条件をクリアできるから、です。
熱抵抗の高い断熱材を入れると、計算上のUA値(断熱の指標)は下がり、補助金の条件をクリアできます。そして、断熱等級の数値も稼ぐことができます。
つまり、設計者や施工者にとっては「成果が見える」形になりやすいのです。
しかし、元々UA値の数字は、透湿や気密とのバランスが取れて初めて意味を持つものです。断熱材を入れただけで「性能が上がった」とは言えないのが現実です。
一時的に数値を上げて補助金の条件をクリアできるかもしれません。しかし、本当に暮らしやすい快適な生活があるのかと言われると疑問が残ります。
断熱リフォームやリノベーションをするのは、補助金の条件をクリアするためにするのかというとそうではありません。断熱リフォームやリノベーションをするために補助金をうまく使う、はずです。
そうなった時に大切なのは、補助金ありきではなく、「本当に必要な断熱リフォームやリノベーション」をすることです。
暮らしは施工が終わることがゴールではありません。そこからが暮らしのスタートなのです。
エビデンスから見えるリスク
スタイロフォームは透湿抵抗が非常に高いです。
μ値と呼ばれる数値はスタイロフォームが100~200程度。土壁は10〜20程度です。
数値が高い方が水蒸気を通さないので、スタイロフォームがどれほど透湿抵抗が高いのかがわかっていただけるかと思います。同時に、両者を重ねれば、流れは逆転し、湿気は滞留してしまいます。
また、建築科学の文献では、外張りにXPS(スタイロフォーム)を使う場合、厚みが足りないと下地裏面で結露が長期間発生し得ることが示されています(Building Science Corporation)。
さらに、Green Building Advisorでは、厚い剛性フォームが「事実上の外側防湿層」となり、湿気の排出が妨げられるためカビや劣化のリスクが高まると警鐘されています。
つまり、XPS自体は水を吸わないものの、その表面や裏側が結露場になり得ることは海外でも確認されているのです。
断熱を考える本当に大事なこと
断熱性能を上げるための3つのポイント
断熱材を入れれば性能が上がる、という単純な話ではありません。
・室内側の気密が確保されているか
・湿気の流れが整理されているか
・出口を塞いでいないか
この三点を押さえなければ、断熱性能の数字は虚ろなものに過ぎません。
内部結露は表面に現れないため、その家に住むあなたが気づくときにはすでに土台や下地が傷んでいる。
だからこそ、「数字だけで判断していないか?」と問い直す必要があります。
また、土壁を活かしたいのであれば、透湿性を持つ断熱材を組み合わせるという選択肢もあります。木質繊維板やセルロースファイバー、羊毛もありかな?のように、湿気を調整しながら断熱性を高める方法です。
逆にXPSをどうしても使うなら、十分な厚みと断熱の連続性を確保し、内側に確実な気密層を設けることが最低条件になります。
本当に快適な暮らしのための断熱リフォームやリノベーションのためにしていること
スタイロフォームと土壁の組み合わせの話を通じ、断熱材と壁の材質の組み合わせの重要性を知っていただけたかと思います。
僕達はいろんな現場を仕事柄見たり監修をすることが多い中で、知ったことがあります。
それは、断熱気密施工のほとんどが「邪魔くさい」や、「これで十分」という現場での知識の欠如があまりにも多いのです。
断熱は断熱材と壁の素材の組み合わせ、そしてニーズにあった断熱材を適切な量入れることが必須です。
それだけではなく、家の隙間に当たる「気密」を徹底すること。これがないと、断熱材を入れても効果がうまく出ないのです。
気密が本当に必要なのか、気密ってなんなのかと思われた方はぜひ下記の記事をご覧ください。
気密はいらない?と思ったら見て欲しい、家づくりの気密の全て
暮らしとは施工した後から始まる。
だからこそ、僕達は「本当に暮らしやすい家」にこだわった家づくりをしています。
家の性能にこだわること。
小さな家のメリットを存分に活かすこと。
住まう人が「本当に快適な暮らし」ができるようにすること。
同時に、僕達が何より声を大にしてお伝えしたいのが、小さい家が暮らしづらいのは設計力が不足している、ということです。
表面積が少ない、小さい家は高性能な住宅にしやすいです。そのため、断熱材をしっかり入れることもできるので、非常に快適な住まいにすることが可能です。
小さい家は設計力次第。
小さい家、最高やん!
そんな僕達の考えや家の性能などの詳細はこちらを是非ご覧ください。
まとめ
スタイロフォームは高性能な断熱材ですが、透湿を遮断するという性格を無視して土壁と重ねると、内部結露のリスクを高めます。補助金や等級の数字を優先しただけの設計では、家の耐久性や快適性を守れません。
無知が一番のリスクです。見えない壁の中で何が起きているのか。そこを理解することが、これからのリノベーションで一番大切な視点になるはずです。
あなたは「数字」だけで家を選びますか?
それとも「見えない壁の中」にも目を向けますか?
家づくりでは空調計画もすごく大切なことです。⬇️
断熱材を入れれば性能が上がる──本当にそうでしょうか。
壁の中で起きる“見えない現象”まで気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの家に最適な断熱と透湿のバランスを、一緒に考えていきましょう。
小さい家?最高やん。