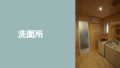なぜ「小さい家=収納不足」と思ってしまうのか?
小さい家 収納 足りない?数字で見るクローゼットの現実
「小さい家に住むと収納が足りないのでは?」――これは家を探す人やリノベーションを考える人が必ず感じる不安です。たとえば延べ床面積70㎡(約21坪)の2LDKに、家族3人で暮らすケースを考えてみましょう。
よくある間取りでは、寝室のクローゼット0.8㎡が2か所、廊下の物入れが1.2㎡ほどで、合計は約3㎡。つまり1人あたり1㎡しかない計算です。
1㎡は「奥行55cm×幅180cm」程度。ここにハンガーをかけると25〜30本が限界です。春夏秋冬の洋服やスーツをすべてしまうには心細い数字ですよね。数字で見ると「やっぱり狭い」と不安になるのは当然なのです。
押入れ文化と“広ければ安心”の思い込み
日本の家では、昔から「押入れ」や「大きなタンス」が定番でした。押入れは畳1枚分ほどの大きさ、つまり約1.7㎡。布団や衣装ケースをまとめて入れるには便利ですが、奥行きが深すぎて物を二重に重ねやすく、奥に入れたものを忘れてしまうことも多い空間です。
それでも「大きな収納がある=安心」という感覚が根強く残っています。大きな箱にしまえば一見片付いたように見えるからです。実際には、奥に押し込んだまま存在を忘れてしまい、使わない物が増えることもしばしば。つまり「広い=便利」とは限らないのです。
収納不足感の正体は「使いにくさ」にある
では、なぜ「小さい家=収納不足」と感じてしまうのでしょうか。その理由の一つは「使いにくさ」です。
例えば、クローゼットの天袋(上の棚)が高さ2m以上にある場合、大人でも踏み台が必要になります。毎日使うバッグや洋服をそこに置くのは現実的ではありません。数字で見れば収納が3㎡あっても、「届かない」「見えない」「重くて出せない」といった状況では、事実上“使えない収納”になってしまうのです。
収納の広さはあっても、それが「生きた収納」になっていなければ、体感としては不足と同じ。つまり不足感の正体は「量」ではなく「質」にあると言えます。見出し4:小さな空間でも使いやすさを優先すれば十分
ここで考え方を変えてみましょう。収納は「入れる場所」ではなく、「使って戻す流れを助ける場所」として考えるのです。
たとえば毎日使うTシャツ。1人あたり20〜30枚あれば十分ですが、これを引き出し2段(幅60cm×奥行45cm×高さ20cm)で管理できます。つまり0.05㎡程度の小さなスペースで足りるのです。
ハンカチなら幅15cm×奥行20cmの小箱で10枚以上入ります。散らかるかどうかは面積ではなく、「必要な量が必要な場所にあるかどうか」。
小さい家であっても、この視点で収納を見直せば「足りない」という不安は大きく減っていきます。
数字に惑わされるのではなく、「暮らしのリズムに沿った収納」を優先する。それが本当に使いやすい住まいにつながります。
第2章 収納は“量”より“質”で決まる
収納率8〜12%という数字の目安
住まいの世界では、床面積に対する収納の割合を「収納率」と呼びます。一般的に**8〜12%が目安とされています。たとえば延べ床60㎡の家なら、収納は約5〜7㎡あれば十分、という考え方です。数字だけ見れば「じゃあ5㎡以上あれば安心だ」と思うかもしれません。
しかしここで注意したいのは、この数字があくまで「統計上の目安」にすぎないということです。もし収納が寝室の隅にばかり集まっていたらどうでしょう。リビングで散らかるリモコンや文房具、玄関で散らかる靴や傘は片づきません。つまり、収納率が高くても“場所が合わなければ使いにくい”**ということです。
小見出し2:配置と動線が家事効率を変える
収納の量よりも大切なのは「どこにあるか」。毎日の生活動線に合わせた配置こそが暮らしやすさを決めます。
たとえばキッチン横に0.5㎡のパントリー(奥行55cm×幅90cm×高さ200cm)があるだけで、食品や飲料の出し入れが劇的に楽になります。ここには2Lペットボトルを24本、缶詰40個以上、乾物や調味料まで一度に収納できます。これが離れた場所にあると、1日で何度も往復するはめになります。
数字で考えてみましょう。もし料理中に収納の位置が悪くて1日20回往復していたら、それだけで10分以上のロス。配置を工夫すればその往復が8回程度に減り、時間は3分程度に短縮。1日7分の節約=年間で約40時間。ほぼ丸2日分の自由時間を生み出せる計算です。
小見出し3:デッドスペース活用で1㎡を増やす方法
小さい家こそ、隙間や余白を活かす工夫が大切です。これを「デッドスペース活用」と呼びます。
- 廊下の壁:厚み10cmでも、幅180cm・高さ220cmの壁面を利用すれば約0.4㎡の収納が生まれます。本なら200冊以上、日用品や書類も余裕で収まります。
- 階段下:高さ1.2m・奥行1.5mの空間は1.8㎡。子どものおもちゃや季節家電(扇風機・加湿器など)を十分にしまえる広さです。
- 洗面所の上部:吊り戸棚(幅90cm×高さ50cm×奥行40cm)を設置すれば、タオル100枚以上をまとめられます。
合計すると、小さな工夫で3㎡以上の収納が追加できることも珍しくありません。これは延べ床60㎡の家にとって、収納率を5%以上押し上げる効果に相当します。つまり「足りない」と感じていた分は、工夫次第で十分補えるのです。
年間60時間を節約する「戻しやすさ」の効果
収納の量よりも、実は「戻しやすさ」が暮らしを大きく変えます。片づけは「入れる作業」ではなく「戻す習慣」です。たとえばリビングに幅60cm×奥行40cmの引き出し1つがあるだけで、散らかりやすい文房具・リモコン・充電器をワンアクションで戻せます。
もしその場所がなければ、物はテーブルや床に置かれ、毎晩片づけるのに10分かかるかもしれません。逆に専用の場所を作れば、戻すのは30秒。差は9分半/日。これを1年続けると約60時間もの差になります。
つまり、収納は「どれだけ入るか」ではなく、「どれだけ楽に戻せるか」で評価すべきなのです。量ではなく質。小さい家ではこれが暮らしやすさの分かれ道になります。
小さい家でも収納は“足りる”と感じられる理由
収納不足は「錯覚」にすぎない
多くの人が「狭い家=収納が足りない」と不安に思います。でも、実際に生活している人の調査を見ると、収納量より“使いやすさ”の満足度が快適さを決めることが分かっています。
たとえば延床60㎡で収納が5㎡しかない家族が「足りている」と答える一方、延床80㎡で収納10㎡ある家庭が「足りない」と感じることもある。数字が多いか少ないかではなく、使い勝手こそが本質なのです。
収納の“見える化”で意外と余裕がある
「足りない」と思っていても、整理してみるとスペースが余るケースはよくあります。
- 押入れに段ボールを重ねたまま、奥が空いている
- クローゼットのハンガーパイプ下がデッドスペースになっている
- 天袋に軽い棚を追加すると、収納量が1.5倍に増える
つまり「収納が小さいから足りない」のではなく、「活かし切れていないから足りなく見える」ことが多いのです。
小さい家は“必要な場所”に収納が寄り添う
広い収納が家の隅にあるよりも、小さくても暮らしの動線に沿った収納のほうが断然便利です。
たとえば、
- 玄関脇に奥行30cmの棚を1つ置けば、靴や傘、リュックをまとめられる
- リビングに壁厚10cmの棚を設ければ、文庫本200冊や文房具を収納できる
- キッチン横0.5㎡のパントリーがあるだけで、食材のストックがすべて収まる
これらはすべて「小さな収納」ですが、生活に直結する“要”の収納。
だからこそ「狭い=足りない」ではなく「小さい=暮らしやすい」に変わっていくのです。
数字で見る“足りる収納”の実例
具体的にシミュレーションしてみましょう。
延床60㎡の2LDK、家族3人の場合:
- 洋服:1人30着 → 幅1.5mクローゼットで十分(約0.8㎡×2か所=1.6㎡)
- 食品・日用品:パントリー0.5㎡+壁収納0.4㎡で足りる
- 季節用品・家電:階段下1.2㎡を利用
合計すると約3.5㎡〜4㎡で暮らしに必要な収納はカバーできます。収納率でいえば6〜7%。目安の8〜12%より小さいですが、「不足」ではなく「ちょうどいい」。
つまり、数字だけで「小さい家は足りない」と判断するのは誤解なのです。
小さい家でも快適に暮らすための実践ステップ
ステップ1 持ち物を3分類する
「収納が足りない」と感じる最大の理由は、収納の量そのものではなく、モノが多すぎることにあります。
まずは家にあるものを3つに分けます。
- よく使う(毎日または週に1回以上)
- たまに使う(数か月に1回)
- 使わない(1年以上出番なし)
この仕分けをリビングや寝室の一部だけでもやってみると、全体の**20〜30%**は「使っていないもの」だと分かるケースが多いです。
つまり「収納が足りない」のではなく「不要なものが収納を占領している」だけ。まずは“余白”をつくることが第一歩になります。
ステップ2 使う場所に収納をつくる
次に考えるのは「どこで使うか」。収納は大きさよりも、動線に沿って配置することが大切です。
たとえば:
- 玄関に幅60cmの棚を置けば、靴・傘・カバンをまとめて収納可能。朝の外出準備が5分短縮。
- キッチン横に0.5㎡の棚を設置すると、2Lペットボトル24本+缶詰40個+調味料類が収納でき、買い出しの度にしまう場所を迷わなくなる。
- リビングに奥行10cmの壁厚収納をつければ、本200冊、文房具やリモコン類もすっきり収まる。
このように「使う場所に置く」だけで片づけ時間が大幅に減ります。
ステップ3 デッドスペースを見直す
小さい家ほど「隙間の宝探し」が重要です。
- 廊下の壁:厚み10cmを利用すると**0.4㎡**の収納棚がつくれ、本や掃除用具がすっきり。
- 階段下:高さ1.2mの空間を活用すれば、扇風機や加湿器など季節家電を丸ごと収納可能。
- 洗面所の上部:吊り戸棚をつけると、タオル100枚分以上を収納できる。
「収納がない」と思っていても、視点を変えるとまだまだ隠れたスペースはあります。
リノベ相談では“量”より“形と位置”を伝える
リノベーションを検討する段階では、「収納は大きく!」と希望を出しがちです。けれども本当に必要なのは「どれくらい入るか」ではなく「どこにあるか」「どう使うか」。
設計者に相談するときは、
- 「玄関で靴と傘をまとめたい」
- 「リビングに子どものおもちゃを片づける棚が欲しい」
- 「キッチンで食品のストックを整理したい」
といった具体的な使い方を伝えることが大切です。これが、限られた空間でも“足りる収納”を実現するコツになります。
小さい家でも収納は足りる
数字で見る「延床60㎡・家族3人」の収納シミュレーション
ここまでの話を整理すると、「小さい家でも収納は工夫次第で十分足りる」ということが分かります。最後に、延床60㎡・2LDK・家族3人という典型的なケースを例に、どれくらい収納があれば暮らせるのかを数字で見てみましょう。
- 洋服:1人30着 × 3人=90着。幅1.5mクローゼット2つ(約1.6㎡)で収まる。
- 食品・日用品:キッチン横のパントリー0.5㎡+リビングの壁厚収納0.4㎡で十分。
- 季節用品・家電:階段下収納1.2㎡に収まる。扇風機・加湿器・季節布団まで対応可能。
- 靴・外出用品:玄関脇の棚0.6㎡で靴20〜25足+傘+バッグが収納可能。
合計すると約3.5〜4㎡。収納率で言えば**6〜7%**程度ですが、暮らしに必要なモノはしっかりカバーできています。つまり、目安の8〜12%に届かなくても「足りない」とは限らないのです。
収納は“量”ではなく“使いこなし”の問題
ここで重要なのは「数字」ではなく「暮らしとの相性」です。
収納が10㎡あっても奥まった場所に集中していれば「不便で足りない」と感じます。逆に収納が4㎡しかなくても、生活動線に沿って配置されていれば「便利で十分」と感じます。
つまり「小さい家は収納が足りないのでは?」という不安は、数字だけで判断しているから生まれるのです。視点を変えれば、「足りない」は「ちょうどよい」に変わります。
視点を変えれば小さい家は快適に暮らせる
収納は暮らしを支える“道具”です。道具の役割は大きさではなく、どれだけ役立つか。
- 玄関に小さな棚 → 朝の準備が5分短縮
- キッチン横のパントリー → 買い物帰りがラクに
- リビングの壁厚収納 → 片づけに迷わなくなる
こうした“小さな工夫”が積み重なると、暮らし全体の効率が上がり、ストレスが減り、心に余裕が生まれます。
「小さい家=不便」ではなく、「小さい家=暮らしに集中できる空間」。これがリノベーションで得られる新しい価値です。
次の一歩は「自分の暮らしを数字で見てみる」
この記事を読み終えたら、まずは自分の家を数字で見直してみましょう。
- 洋服は何着あるのか?
- 靴は何足あるのか?
- 食品や日用品のストックは何日分あるのか?
数字にすると「思ったより少ない収納で足りる」ことに気づけるはずです。そこから「どこに置けば戻しやすいか」を考えることが、快適なリノベーションへの第一歩になります。
まとめ
「小さい家は収納が足りないのでは?」という不安は、実は錯覚です。量より質、数字より配置。
工夫すれば、延床60㎡の家でも家族3人が快適に暮らすだけの収納は確保できます。
大切なのは「もっと大きく」ではなく「もっと便利に」という発想。そうすれば、小さい家はむしろ暮らしやすい家に変わります。