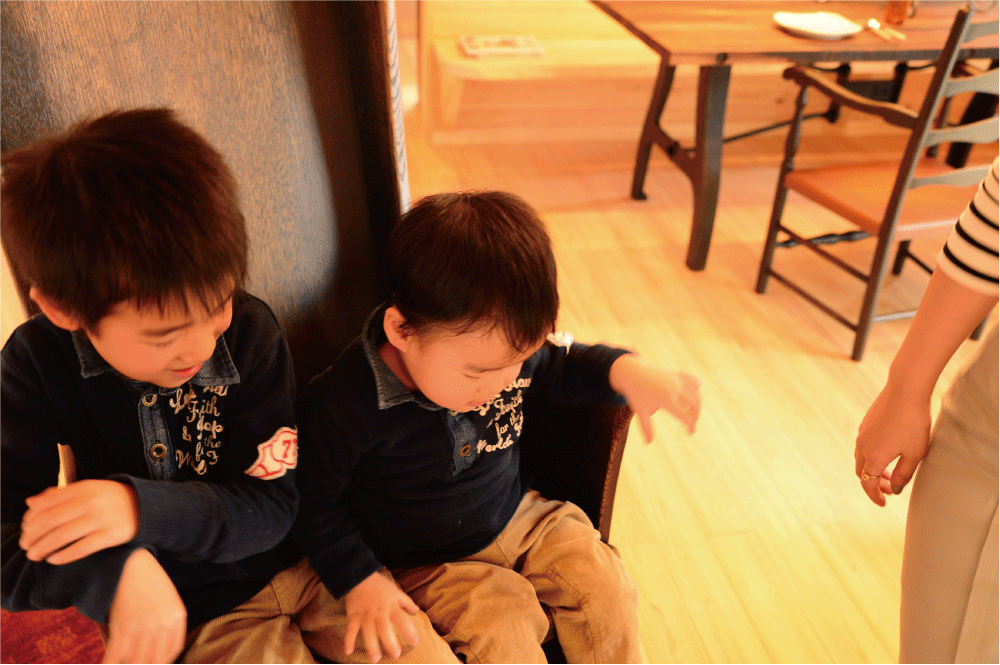断熱リフォームをしたのに寒い人が多い本当の理由
「断熱したのに寒い」「結露が増えた」──よくある後悔
「せっかく断熱リフォームをしたのに、冬になると足元が冷たいまま。」
「お風呂は綺麗になったのに脱衣所で震える。」
「部屋の空気がこもって、結露やカビが前より増えた気がする。」
僕のもとには、こうした 断熱リフォームで後悔した人 からの相談が後を絶ちません。
リフォームしたのに寒いのは当たり前?
多くの人が「断熱材を入れれば暖かくなる」と思い込んでいます。
でも実際は、
- どこに断熱を入れるか
- どう空気を入れ替えるか
- 部分的に冷たい場所をどう防ぐか
を考えないと、リフォームしても寒さは残ります。
目に見える満足と、暮らしの本当の満足は違う
新しいキッチンやお風呂は、誰が見てもわかる変化です。
でも、床の冷たさ・脱衣所の寒さ・寝室の結露 は、見た目ではわかりません。
リフォーム直後は「新しくなって嬉しい!」と感じますが、
冬が来るとまた同じ不満が戻ってきます。
断熱リフォームは、家の「当たり前」を整えるもの
僕はよく、
「断熱はぜいたくじゃなく、家の基本です」
とお伝えしています。
暖かさ、結露しない、空気がこもらない、
これらは特別な機能ではなく、
家として当たり前に欲しいこと。
だからこそ、
見た目を変える前に寒さの根っこを絶つ
それが断熱リフォームで後悔しない方法です。
寒さが残る家に共通する3つの落とし穴
「床だけ冷たい」「結露が止まらない」原因は一つじゃない
「リフォームしたのに足元だけ冷たい」
「寝室の窓に毎朝びっしり結露がつく」
「部屋の空気がどんよりして匂いがこもる」
これらは、どの家にも共通する3つの見落としから生まれます。
1. 部分的に断熱が抜けている
よくあるのが、リビングは暖かいのに廊下や脱衣所は寒いまま。
これでは暖かい空気が外へ逃げて、床が冷たい家になります。
またよくある結露の原因にも繋がります。
断熱は「全体のバランス」が命。
壁だけ、天井だけ、では意味がなく、
床や窓からも熱は逃げます。
2.室内空気の入れ替えを自然な形で行えない
せっかく断熱しても、空気がこもる家では体感は変わらないように感じます。
- キッチンの匂いが抜けない
- 湿気が溜まって結露しやすい
- どの部屋も空気がモワッとしている
これらは、窓の位置や隙間風を減らすだけでは解決できません。
室内空気が自然と入れ替えされるように入口と出口を設計することが、実は一番大切です。
3. 結露・カビの温床を作ってしまう
「暖かい家にしたい」と思って断熱材を詰め込んだ結果、
壁の中に湿気がこもり、結露やカビが発生する例が本当に多いです。
本来、断熱は湿気対策とセットで考えるもの。
家の中に余分な湿気を残さないための「換気の道筋」を作らないと、
見えない場所で家が傷んでいきます。
寒さも結露も、根っこは同じ。順序の問題です。
まとめると──
「断熱リフォームで後悔する家」は、
どこも 断熱・空気・湿気 の順序が間違っています。
- 部分的に寒い
- 匂いがこもる
- 結露がひどい
これらは全部つながっています。
断熱リフォームを単体で考えることで良く悩まれる方がおられます。正直なところ、目に見えないものにお金をかけることへの心理的な圧迫はあります。ですが、僕はいつも「耐震も含めてトータールで考えていきましょう」と話をしています。
もし、何か断熱リフォーム・・・と引っかかるなら一度この記事も読んでみてください。
下の画像をクリックすると記事が読めます。
寒さも結露も防ぐ、正しい順序と空気の通り道の考え方
「どこに断熱を入れるか」より大切なこと
多くの人が、断熱材をどこに入れるかばかりに意識が向きます。
でも実は、その前に考えるべきことがあります。
それは、
「家の中の空気をどう入れ替えるか」
です。
これを飛ばしてしまうと、どんな高性能の断熱材を入れても体感は改善されません。
暖かい空気が巡る家は寒さが残りにくい
例えば──
- リビングで暖めた空気が廊下に流れない
- 玄関で冷たい空気が吹き込む
- 寝室に空気が溜まってジメジメする
こうした状態では、部分的に寒い場所が必ずできます。
逆に、空気の通り道を作ると
家全体の温度がゆっくり均一になり、
寒さも結露も起こりにくくなります。
「換気」ではなく「通り道」を設計する
「24時間換気システムがついているから大丈夫」と思いがちですが、
機械だけに頼っても、空気は思い通りに動きません。
空気の通り道を作るには、
- 廊下や階段をうまく使って空気が回るようにする
- 吸気口と排気口を家の対角に配置する
- ドアの下にスリットをつけて空気が止まらないようにする
こうした小さな工夫が、
「空気がこもる家」を根本から変えます。
断熱と気密は「空気を動かす準備」
気密を高めるのは、外の冷たい空気を無駄に入れないため。
その上で、家の中の空気を「どこから入れて、どこから抜くか」
これを決めるのが換気計画です。
そして最後に、必要な場所に断熱材を入れる。
これが、結露しない・寒さが残らない家をつくる順序です。
設計で空気を味方にする
僕が現場でいつも意識するのは、
「この家の空気はどこからどこへ流れるのか?」ということ。
- 冬は暖かい空気がゆっくり巡る
- 夏はこもった湿気が自然に外へ抜ける
- 料理の匂いもすぐ外に出る
こうした小さな工夫が積み重なると、
エアコンに頼りすぎずに快適な家が叶います。
リフォームは全部やれなくてもいい。部分断熱で暮らしを変える方法
「断熱リフォームを全部やらないと意味がない」と思い込んでいませんか?
リフォームの相談でよく聞くのが、
「どうせ予算が足りないから、断熱は諦めた」という声です。
確かに、家全体を一度に断熱するにはそれなりの費用がかかります。
でも、全部できないからといって、何もしないのは本当にもったいない。
部分断熱でも体感の7割は変わる
実際、僕が現場でやっているのは、
「使う場所から断熱する」 という考え方です。
たとえば:
- 長くいるリビングを優先して床と窓を断熱
- 洗面室や脱衣所を断熱してヒートショックを防ぐ
- トイレなど寒さが身にしみる場所を先に手を入れる
こうするだけで、家の寒さはぐっと和らぎます。
冬の暖房代も抑えられるので、費用対効果はかなり大きいです。
優先順位をつければ、無理なくステップアップできる
「予算が足りないから何もできない」ではなく、
「まずここだけでもやる」という順番を決める ことが大切です。
例えば:
- 床下の断熱 → 床が冷たいを解消
- 窓の内窓 → 熱の出入りを減らす
- 洗面所と脱衣所 → お風呂上がりの寒さ対策
こうしておけば、将来予算が貯まったときに
追加で壁や天井の断熱をしても無駄になりません。
部分断熱は「妥協」ではなく「戦略」
一部だけでも手を入れると、
暮らしの快適さが確実に変わります。
- スリッパがなくても冷たくない床
- 夜中のトイレで震えない
- お風呂上がりの湯冷めがなくなる
小さな変化の積み重ねが、
「断熱してよかった」と感じる毎日の安心につながります。
後悔しないために、解体のタイミングを逃さない
もう一つ大事なのが、
水回りのリフォームをするタイミングです。
キッチンやお風呂を新しくする時は、
必ず壁や床を壊すので、そのときに断熱を一緒にするのが一番お得です。
壊した後に断熱を入れないのは、本当にもったいない。
部分断熱を上手に計画すれば、工事のムダも減らせます。
断熱工事は家全体をしないといけない。と思われている方が多いです。
ですが、しっかりとした計画次第では部分的に断熱を補強することで、体感が改善されます。
この部分断熱について詳しく書いた記事を、お時間が許すなら読んでみてください。下の画像をクリックすると記事が読めます。
素材より大事なのは「誰がどう施工するか」
「どの断熱材が一番いいですか?」とよく聞かれます
「セルロースファイバーが自然素材で良さそう」
「羊毛断熱って体に優しいんですよね?」
「グラスウールって安いけど大丈夫ですか?」
──リフォーム前の相談で、必ずと言っていいほど聞かれるのが
どの断熱材が一番良いか? という質問です。
でも、実はこれ、答えは一つじゃありません。
素材だけで暖かさは決まらない
どんなに高性能な断熱材でも、
入れ方や施工が間違っていると、半分も力を発揮できません。
例えば:
- グラスウールはコスパが良いけれど、丁寧に隙間なく詰めないと意味がない
- セルロースファイバーは吸音性も高いけど、吹き込みの密度が甘いと効果が落ちる
- 羊毛断熱も、通気や湿気対策とセットで考えないと結露の原因になる
つまり、素材だけで家が暖かくなるわけじゃない んです。
大切なのは「設計」と「施工」
家の寒さをなくすには、
1️⃣ どこを断熱するかを決める設計
2️⃣ 正しい手順と方法で断熱材を入れる施工
3️⃣ そして、空気がこもらない通り道を一緒に作る換気の工夫
この3つが揃わないと、
どんなに良い素材を選んでも「結局寒い」「結露が増えた」という後悔が残ります。
信頼できるパートナーが一番の断熱材
結局のところ、
「どの素材を選ぶか」より、「誰に頼むか」の方が大切 です。
現場を知っていて、
家全体の空気の動きまで考えてくれる人と一緒に進めれば、素材の力を最大限に活かせます。
素材を信じる前に、人を信じる
「断熱材にこだわったのに寒い家」
そんな悲しい話を一つでも減らすために、
僕はいつも現場で、「設計と施工こそが一番の性能だ」と伝えています。
断熱リフォームはぜいたくじゃない ─ 毎日の「当たり前」を守るもの
「うちには贅沢かな」と思わないでほしい
「設備を新しくするだけで予算がいっぱいだから、断熱は後でいいかな」
「見た目を綺麗にするほうが大事だし…」
こんなふうに考える人は少なくありません。
でも僕は、いつもこう言います。
断熱は贅沢じゃない。
家族の健康と暮らしの当たり前を守る、最低限の設計です。
暖かさは特別じゃない、当たり前にしていいこと
冬でも足元が冷たくない
部屋ごとの温度差が少ない
結露が出ない
空気がどんよりこもらない
光熱費が必要以上にかからない
こうしたことは「高級住宅だから叶う」わけではありません。
正しい順序と、必要な場所に必要な断熱を入れれば、
どの家でも無理なく手が届きます。
見た目より、暮らしの質が長続きするかどうか
キッチンやお風呂は10年後には古くなります。
でも、断熱や気密、空気の通り道は、
家がある限り暮らしを支え続けてくれます。
設備は入れ替えられても、
冬の寒さや結露は「あとで直す」が一番お金がかかる。
だからこそ、最初にしっかり考えておくのが、
結果的に一番賢い方法です。
「全部やれないから何もしない」は一番もったいない
すべてを一度に完璧にする必要はありません。
優先順位をつけて、できるところから一歩ずつ進める。
部分断熱でも、空気の流れを作るだけでも、
暮らしの質はしっかり変わります。
家族の「なんとなくの我慢」をなくそう
- スリッパがないと冷たい床
- お風呂上がりに震える
- 朝起きると窓がびしょびしょ
- 部屋がカビ臭い
これらは本来、我慢しなくていいことです。
断熱リフォームは、そんな「小さな我慢」を手放すための一歩です。
さあ、暮らしの“当たり前”を整えるところから始めよう
今、考えるだけでも充分です。
もし迷ったら、まずは優先順位を決めるだけでも構いません。
小さな選択が、
毎日の安心と心地よさを支えてくれます。
色々なお悩みも、間取りや設計の視点で一緒に考えていけます。
京都での改修・リノベーション、狭小住宅の設計についてのご相談もお気軽にどうぞ。

この記事おすすめの方
・見積もりを渡されてもどこをみたらいいのかわからない方
・お金をかけるべき場所、削っていい場所を自分で判断できるようになりたい方
この記事を読むとできるようになること
・見積もりの内訳を理解できる
・どこを削っていいか否かを自分で判断できる
・工務店の見積もりの根拠がわかる
無料、無登録で読める
見積もり読解ガイドのリンクはこちら↓