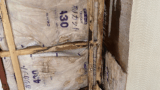中古住宅は古くて寒い、不安の正体は構造の性能不足
京都の中古住宅のイメージ
京都で中古住宅を購入し、リフォームを計画する際、頭をよぎるのは決まってこの言葉ではないでしょうか。「でも、やっぱり寒そうですよね?失敗したくないのに…」。
これは単なるイメージではありません。
多くの人が、子どもの頃の記憶や過去の体験から体で覚えた不信感からきています。
例えば、以下のようなものがあります。
・祖父母の家の廊下が、足がしびれるほど冷たかった。
・冬のトイレや脱衣所が辛く、寒さに耐えて、暖かい部屋に逃げるように戻る。
・ストーブの前から離れられず、光熱費ばかりがかかる。
これらの経験から、「お金をかけても、結局寒さが改善されないのではないか」という不信感が根底にはあります。これは、あなたの暮らしの本質に関わる恐怖です。
地域の特性とリフォームの盲点
京都の気候で注意すべき点は以下の通りです。
・底冷え: 京都の盆地特有の気候です。冬の冷気が足元に溜まり、芯から冷えます。
・湿気: 夏は高温多湿です。古い家の構造が湿気をため込み、カビや劣化の原因になります。
京都の気候は、「底冷えと湿気のダブルパンチ」なのです。
そのため、リフォームするときにこの地域特性を理解した上で設計施工をする必要があります。
でも、本当にそうなのでしょうか。
ここからは僕達がどうしてそう伝えるのか、失敗する人の共通点や、今後のリフォームで失敗を予防するためのポイントなどを解説していきます。
中古住宅リフォームが失敗に終わる、後悔する人の共通点
「できる限り早く冷えを解消したい」。
「失敗しない方法を自分のリフォームに生かしたい」。
このように考える慎重な方ほど、以下のような失敗に陥りがちです。
失敗パターン:構造的なリスクを無視するリフォーム
「キッチンやお風呂を新しくしたし、これで快適になったはず!」。
しかし、その満足感は最初の3ヶ月だけで終わるかもしれません。
リフォームで大切なのは、「見映えではなく、空気がどうなのか」という点です。
構造をそのままにしておくデメリットには、例えば、以下のような点があります。
1)体感が改善しない
見た目や機能は変えられます。しかし、空気の質、温度、湿気は「構造と設計」でしか変えられません。キッチンの見た目が綺麗になっても、根本原因となる構造がそのままになっていること。これでは、床の冷たさは改善されておらず、同じ問題に悩まされてしまうのです。
窓を開けたままでいくら暖房をつけても、窓が開いてている状態が改善されなければ、いつまでも寒いままなのです。
2)構造的リスクの無視
中古住宅の冷えの正体は、目に見えない構造の問題です。例えば、床下断熱の欠如や壁・天井の断熱不良などが挙げられます。ここに対処しないリフォームは、お金をかけたのに寒いままという結果を招きます。
断熱材は家の中の温かさを保ち、外部の冷気を遮断するための、いわば家のダウンジャケット。
そのため、断熱材が入っていない時点で家の中は寒いままになってしまうのです。
失敗パターン:補助金に振り回されてしまう
お得にリフォームするために是非とも考えたいのが補助金です。
もちろん、補助金は活用すべきですが、必ず注意して欲しいことがあります。
それは、「補助金があるからリフォームをするのではなく、リフォームをしたいから補助金を使うこと」を明確にすることです。
例えば、補助金要件のために、断熱等級をギリギリ満たす「窓交換だけ」で満足してしまうこと。
確かに、窓のリフォームは断熱性能を上げるためには最大の効果を発揮足ます。
しかし、全体のバランスが整わない状態で窓の取替リフォームだけでは、暮らしやすさには直結しません。それに、窓を新しくしても、壁や床から冷気が漏れていれば、ヒートショック対策としては不十分です。
補助金の範囲で施工しようという気持ちが先行するあまり、本当に必要だった施工部分を「予算オーバーだから後回し」にしてしまうのです。外側の数字や、見た目だけ整えたような、中身が空洞の家になり、冷えの解消には繋がりません。
「補助金制度ありき」で設計を進めると、暮らしの本質からズレた選択をしてしまいます。
僕達が考える正しい順番は、これです。
「まず暮らしの課題(寒さ・湿気)を言語化し、設計と断熱の優先順位を整理する。そのうえで、補助金の条件に寄せていく」。
断熱リフォームは「未来への再投資」である
まず、声を大にしてお伝えしたいのが、断熱にお金をかけるのは贅沢ではありません。それは、「快適に生き直すための投資」であり、未来の自分と家族の健康に贈る、静かなプレゼントです。
断熱がしっかり効いている家では、暮らしの質そのものが底上げされます。
健康面の向上
断熱機能が向上すると、魔法瓶で飲み物の温かさが保たれるように、家全体の温かさが保たれます。それによって、部屋ごとの温度差ができにくく、ヒートショックの予防に繋がります。ヒートショックは高齢の方だけではなく、若い方でも起こりうるため、予防できるのは健康面としては非常に重要です。
また、結露が起こりづらく、結露によるカビ・アレルギーのリスクが減ります。目に見えるところの結露はまだしも、注意が必要なのは、家の見えない部分での結露です。いつの間にか家の壁の中で結露が起こり、カビが大発生している、ということもあるのです。
家の見えない部分での劣化が進んでしまうと、家の資産・投資価値にも大きく影響します。
それだけではなく、見えない劣化を放置すると5年後、10年後に大きな出費に膨らむこともあります。リフォームする時には、部分的ではなく、一度住宅の見えない劣化も含めて現状を知ることから始めるのを、僕達は強くお勧めしています。
光熱費の削減
忘れてはいけないのが、光熱費の削減です。
断熱がしっかりできると、家の中を一度温めると室温が保たれます。そのため、何度も暖房をつけて温め直す必要もなくなります。それによって、暖房効率が上がり、無駄なエネルギーを使わなくなります。
僕達Greener’s Houseが作っている家は、「本当に快適な、高性能で小さい家」です。
断熱がしっかりされていることで室内が暖かく保たれることはもちろん、換気がしっかりできる、収納がたっぷりある、抜け感があって開放感があるなど、小さい家の本当の快適さを提供しています。
高性能の小さい家専門のGreener’s Houseの家づくりについてはこちら
リフォームで失敗しないための3つの優先すべき設計
中古住宅は、単に古い家ではありません。それは、古い家の中に新しい「空気」を設計し直す、最高のチャンスです。あなたの「失敗したくない」という思いに応えるため、僕達は以下の設計の優先順位でリフォームを提案します。
まず、最優先事項は、「冷えの正体である構造の内側を整えること」です。
失敗を防ぐには、見た目ではなく、構造の内側を先に整えることが必須だからです。
床断熱の徹底
床断熱で大切なのは、床下に断熱材を入れるだけ、にしないことです。実は、快適に過ごすためには、床下の空間そのものを「外部」から切り離す設計が必要です。
他にも、基礎断熱や、高性能な床下断熱材を隙間なく施工します。こうすることによって、足元からの冷気を完全にシャットアウトします。
壁と屋根の断熱材
断熱材の種類には、グラスウール、ウレタンなどがあります。断熱材の種類にこだわることも大切ですが、R値(熱抵抗値)やUa値(外皮平均熱貫流率)といった性能を数値で保証してもらうことも大切です。
壁と屋根に適切な厚みと高性能な素材を入れることで、初めて断熱は機能します。外の冷気や熱気をほぼそのまま通す構造を改善します。
窓・玄関の高性能化
冬場に窓の近くに行くと冷気を感じることは多々あるかと思います。窓から逃げる熱は、家から逃げる熱のなんと50%以上を占めるのです。
「樹脂サッシ」と「Low-E複層ガラス」は最低条件。そこに、予算が許せば、トリプルガラスも検討し、熱損失を徹底的に防ぎます。
せっかく断熱材をしっかり入れたのなら、窓も断熱がしっかりしていないともったいないです。より快適な家のためにも、特に大きな窓のある家には大切です。
中古住宅リフォームにおける性能の担保と保証
どんなに高性能な断熱材を入れても、隙間風や湿気があれば、その効果は半減します。これを防ぐには、気密性能(C値)の確保と、湿気コントロール(防湿層)、そして計画的な換気システムの設計が必須です。
なぜ小さい中古住宅のリフォームで高性能住宅にできるのか
高性能の住宅とは「断熱、気密、換気」の3が揃っていることが最低条件です。しかし、京都の場合は湿気なども多いため、湿気のコントロールもまた大切になってきます。
中古住宅のリフォームを考えた時、快適な暮らしをしようと考えると、高性能住宅にリフォームすることが非常におすすめです。ここで、僕達がお勧めしているのが高性能の小さい家です。
僕達は京都の中古住宅リフォームの中でも「小さい家」を専門にしています。
小さい家は、断熱材をたっぷりと入れても表面積が小さい分費用も抑えられます。気密や換気などの性能は小さいからこそ施工が隅々まで行き渡りやすいという良さもあります。
小さい家?最高やん!
そう心から思うからこそ、「本当に快適な小さな家」を提供しています。
高性能住宅にする上で、小さい家は本当に最適です。
特に、断熱はもちろん、気密に関しては客観的なデータとなるC値を取るなど、徹底しています。
気密や換気についてはこちらに詳細に解説しているのでこちらも合わせて是非ご覧ください。
実は資産・投資価値をも上げる断熱リフォーム
気密や換気を含め、断熱リフォームもしっかり行うことは結果として資産・投資価値を高めることにも繋がります。断熱リフォーム、というだけではありません。
その先にある、「資産・投資価値」そのものを見越してメンテナンスしておくこともまたとても大切です。たかが断熱リフォームと思っていても、その時に一緒に見えない劣化をメンテナンスしたり、性能を持たせることで、結果として快適さ以上のものを手に入れることができるのです。
今すぐ「失敗しない」計画を私たちと始めませんか?
今の家が冷える。
今後は冷えに悩まされない家に住みたい。
そう考える方には特に、構造から根本的に解決する断熱リフォームをおすすめします。
特に僕達は不必要なら不必要、必要なら必要な分だけ、を徹底しています。本当に必要なものを必要な分だけの施工で行うこと。住まう人が納得できて、本当に快適な小さい高性能な家作りをしませんか?
気になることがある、質問があるなどはこちらからメールでご連絡ください。
ご質問などにお答えした後、営業メールなどは致しませんのでご安心ください。
お一人おひとりのご不安などに寄り添い、家づくりの力になれれば嬉しいです。