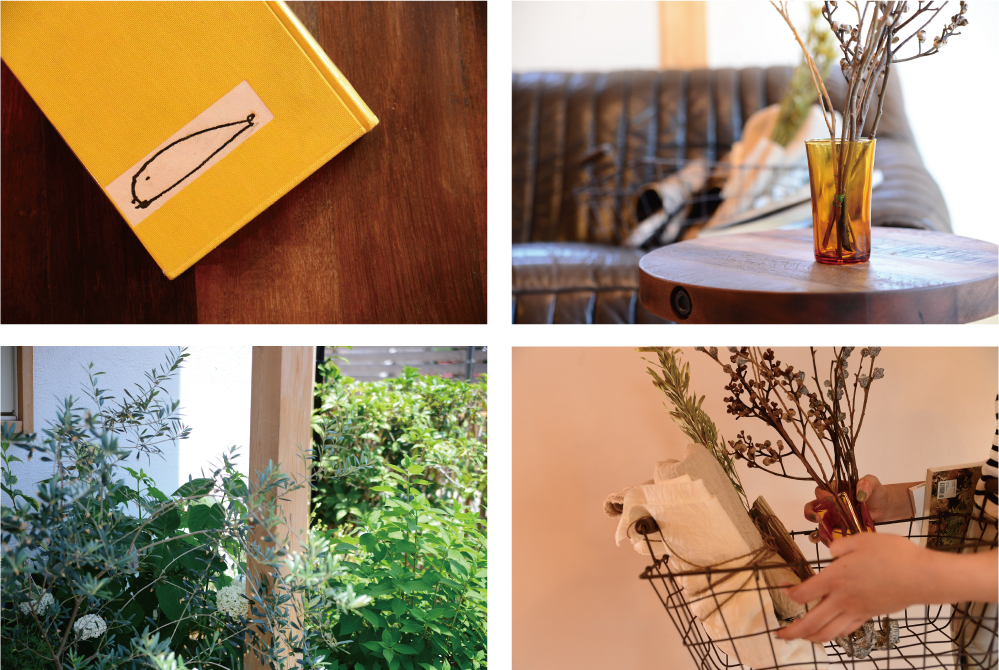結露やカビが多いのは“古い家だから”だと思っていませんか?
「うちは築年数も古いし、カビが出るのは仕方ないよね」
そんなふうに、いつのまにか“あきらめ”が前提になっていませんか?
でも本当は、築浅の住宅でも、リフォーム直後でも──
カビは“起きるべくして起きている”現象なんです。
特に最近は、高気密・高断熱の住宅で、
壁の中や天井裏に「結露によるカビ」が発生するケースが急増しています。
見た目ではわからない。
壁紙はきれい、床もサラサラ。
けれど──
中を開けると、石膏ボードの裏が真っ黒になっていた。
「掃除してもカビ臭が消えない」
「空気がよどんでいる感じがする」
そんな違和感の裏には、“壁の中が濡れている”という真実が隠れているかもしれません。
「内部結露が起きる“3つの条件”──壁の中が濡れる理由」
結露は「窓だけ」の話じゃない。
壁の中でも、静かに進行している。
多くの人が、結露といえば「冬の窓に水滴がつく現象」と思っています。
けれど実際には──
壁の中、床下、小屋裏など、“見えない場所”でも結露は起こります。
そしてそれが、カビの発生・空気の劣化・住まいの腐朽に直結する。
しかもこれは、たまたま起きたのではなく、**“条件が揃って起きた現象”**なんです。
内部結露が起きる“3つの条件”
条件①|湿気を含んだ室内空気が壁体内に侵入する
- 気密が切れている
- コンセントボックス周りや天井部分の気密が悪い
→ 室内の湿った空気が構造の中に漏れ込む
条件②|壁体内で“露点温度”を下回る箇所がある
- 室内の空気が冷やされ、結露が発生
- 断熱層が薄かったり、部分的に欠損している
→ 壁の中に冷たいゾーン(結露帯)ができる
条件③|湿気が抜けずに溜まる“袋構造”になっている
- 通気層がない or 連続していない
- 防湿ライン・透湿ラインが混在している
→ 壁内に湿気が停滞し、カビの温床になる
結露とは「空気の動き」と「構造の重なり」が崩れた結果
これはただの“温度差”の話ではありません。
むしろ重要なのは、空気の流れと構造の精度です。
- 空気がどこから入り、どこに抜けていくのか
- 気密と断熱は、連続して施工されているか
- 湿気はどこに滞留し、どこで抜けられるのか
これらがほんの一箇所でも破綻していると、内部結露は必ず起きます。
「素材が濡れている」のではない。「空気が崩れている」のです。
この現象を、単に「グラスウールがカビた」と見るか、
それとも「空気設計が崩れていた」と見るかで、
家の未来は大きく変わります。
目に見えない湿気の流れが、
素材を腐らせ、においを生み、空気を壊す。
だから僕たちは、断熱材を選ぶ前に、空気の動線を設計する。
中途半端な断熱が“湿気の袋”をつくる
|内部結露が起きる構造的背景と、現場でよく見る症例たち
昔の家は“ゆるさ”でバランスを取っていた
かつての家──とくに昭和〜平成初期までの住宅では、
そもそも「気密・断熱」の考え方がまだ浸透していませんでした。
壁の中にはグラスウールが“とりあえず”詰められ、
気密シートもなく、隙間風が当たり前。
でも、だからこそ──
湿気は出ていく余地があった。
つまり、内部結露は「起きていた」けれど、
深刻なカビや腐朽にまで至らず、“自然に逃げていた”側面があるんです。
今の中古住宅に起きているのは、“逃げ道を失った結露”
近年リフォームされた中古住宅では、
中途半端な知識とコスト主義によって、
中途半端な断熱と気密が施工されているケースが非常に多い。
- 気密ラインが天井で切れている
- 防湿シートが部分的にしか貼られていない
- サッシや配管周りの処理が甘い
- 断熱材が浮いている/湿気を抱え込んでいる
その結果、こうなる:
「湿気が壁の中に入ったら、もう出られない」
→ そして、静かに結露 → カビ → 構造の腐朽へと進行していく。
これは**“閉じ込めた湿気”によって壊れていく家**の典型パターンです。
現場でよく見る「カビ・結露構造パターン」
📌パターン①|グラスウールが水分を含んで垂れている
→ 湿気を吸った断熱材が重みで垂れ下がり、断熱欠損と空気の滞留ゾーンを生む
→ 下がった箇所に冷気が集中し、結露とカビの“ホットスポット”になる
📌パターン②|防湿ラインが施工途中で止まっている
→ 湿気が侵入し、気密破綻箇所から広がる
📌パターン③|通気層が取られていない or 止まっている
→ 湿気が逃げられず、内部に滞留しカビの温床に
📌パターン④|施工中に濡れたまま塞がれた壁体
→ 一度入った湿気が乾かず、密閉空間で腐敗進行。これが意外と原因としては多いのが事実です。
「それ、昔の家では起きなかったことですか?」と聞かれるなら──
僕はこう答えます。
昔の家では、確かに起きていた。
でも、それでも家は持ちこたえていた。
湿気が逃げていたから。空気が動いていたから。でも今は、空気を止めてしまった。湿気を閉じ込めてしまった。
“中途半端な高性能”が、家を壊している──それが今の現実です。
「3層の守り」で内部結露を止める
これは僕がリノベーションで必ず意識する、構造的な湿気コントロールの鉄則です。
① 室内側:気密+防湿ライン
- 可変透湿気密シート or ポリエチレンフィルムを、室内側に連続施工
- 貫通部(配線・配管)は気密テープでしっかり処理
- 天井と壁の取り合い部は気流漏れの盲点なので要注意
→ 室内の湿気を「壁の中に入れない」第一防衛ライン
② 断熱層:密着精度と素材選定
- 柱間にグラスウールをしっかり密着させる(たるみ・浮きNG)
- 垂れ下がったグラスウールは、湿気を溜めて結露帯を生む
- 場合によっては、現場発泡ウレタンとのハイブリッドを選択
→ 断熱のムラが湿気の停滞ポイントになることを防ぐ
③ 外壁側:透湿防水シート+通気層
- 水は通さず湿気だけを逃がす**透湿防水シート(例:タイベック)**を外壁側に施工
- その外側に15mm程度の通気層を確保し、壁内の湿気を“出口”に誘導
- 通気層の上下(軒天〜基礎)まで、空気が通り抜けるルートが開通しているか確認
→ 湿気が「抜けない構造」は、“袋の中でカビを育てている”のと同じ
※補足:
通気層や透湿防水シートは、「外壁の仕上げ材の内側」にあります。
つまり、これらを新たに設けたり修正したりするには、外壁材を一度剥がす必要があるケースも少なくありません。
リフォームでこれを行うには、構造や予算のバランス、施工体制の確認が必須になります。
だからこそ僕たちは、ただ断熱材を追加するのではなく、
“通気層まで含めた全体構造”として湿気の逃げ道を設計する必要があるんです。
「断熱」とは、湿気を止めることではない
→ むしろ、“湿気が抜ける道を設計すること”
高性能住宅=断熱材をいっぱい入れること
と思っている人はまだ多い。
でも僕たちが知っているのは──
湿気の逃げ道を封じた断熱は、ただの湿潤地獄になるという現実です。
だから断熱・気密・通気は、必ず“セットで重ねて”考える。
それが、家をカビさせないための構造的処方箋です。
湿気は“防ぐ”のではなく“逃がす”
|内部結露を止めるための、空気・断熱・通気の設計3層構造
湿気は、絶対に入ってくる。
まず、大前提として僕が伝えたいのはこれです。
湿気は、どれだけ頑張っても「防ぎきれない」。
呼吸、調理、お風呂──
日常生活そのものが、水蒸気を生み出しています。
さらに外気にも、梅雨や台風の時期には大量の湿気が含まれています。
だから僕たちは、こう考える。
湿気は“入ってくるもの”と認めた上で、「通して」「逃がす」ことを設計する。
結露のない空気は、素材も暮らしも整える
|湿気を逃がす設計が、家に「軽さ」を取り戻す
「においがしない」って、実はすごく贅沢なこと
壁の中が乾いている。
押し入れを開けても、カビ臭くない。
冬の朝でも、サッシが濡れていない。
──それって、**住んでいると気づかないほど“静かだけど、大きな変化”**です。
空気が整っていると、
素材の手触りも、においも、音の響きも変わる。
そして、住んでいる人の身体も、少しずつ変わってくる。
「朝起きたとき、咳が出なくなった」
「洗濯物ににおいがつかなくなった」
「なんか、家の中が軽くなった気がする」
それは偶然ではありません。
湿気の逃げ道を、ちゃんと設計した結果です。
自然素材は、“空気が整っている”ことで性能を発揮する
無垢材、漆喰、和紙、珪藻土。
自然素材は、確かに調湿性を持っています。
でも、「湿気が排出される設計」があってこそ、素材は呼吸する。
空気がよどんでいて、湿気が抜けない構造の中では、
いくら自然素材を使っても、逆に素材が傷みやすくなってしまう。
だから僕たちは、素材を使う前に、
その素材が“ちゃんと働ける環境”を先につくる。
それが「空気を設計する」という考え方です。
空気が整うと、暮らしが整っていく
この仕事をしていて、いちばん嬉しいのは──
リノベが終わったあと、施主さんがこう言ってくれる瞬間です。
「なんか、家の中が気持ちよくなりました」
「別に見た目は変わってないけど、空気が違う気がするんです」
それは、断熱性能が良くなったとか、素材が高級になったとかではなく、
空気と湿気の“目に見えない流れ”を丁寧に整えたからこそ、起こる変化。
そしてそれは、これから先の10年、20年の暮らしを守ってくれる設計なんです。
この記事が人気です。ぜひお読みください↓
カビのない家?|空気と湿気の設計で失敗を防ぐ5つの視点
暮らしを変えるために必要なのが空気設計
家の中が息苦しい、を変える空気設計
内部結露の止め方なども紹介しました。
ですが、大切なのは結露ができたから対処するのではなく、結露しない環境を作ることです。
家の中が息苦しい。空気が重い。
そう感じるのは、湿度の高い空気がこもってしまうことが多くの原因です。
それを解決し、結露もカビも予防する。
このために必要なものが、湿気を逃すための空気設計をすることです。
湿気を逃すことでそもそも結露する水蒸気を外へ逃し、根本原因を断ち、カビを予防するのです。
この時、とても大切になるのが気密です。
空気設計通りに換気するには気密が必須
気密とは、家の中の隙間をなくすことです。
一見それでは湿気が逃げなくなると思われがちですが、そうではありません。
家の中をしっかりと密閉し、適切な窓を開けることによって、空気の流れをコントロールするのです。
これこそが空気設計であり、本来の換気能力になります。
空気設計通りに換気をしないと、ある部屋は換気ができて、ある部屋は換気不十分という差が生まれてしまいます。
空気は近い場所に楽をするように流れる性質があります。
そのため、1つの部屋で2つの窓を開けると、もう家の奥には空気は流れなくなるのです。
だからこそ、家の中の湿気を全て取り去るには、家全体に空気の流れを生み出す必要があります。
それこそが空気設計であり、空気設計通りに家の中が換気されることが重要なのです。
空気設計通りに換気するために必要な気密については、こちらの記事で解説しています。
空気が重いを解決する家作りの条件
では、具体的にどんな家が湿気を溜め込まない、換気の行き届いた家になれるのでしょうか。
これを考える時に僕達がオススメしているのが、「小さな家」です。
小さな家と聞くと、狭くて、空気もこもっているようなイメージがあるかもしれません。
でも、実は小さい家は設計次第で、大きな家をはるかにしのぐ快適な家になるんです。
理由はたくさんありますが、大きく挙げると、以下の通りです。
・施工時に気密しやすい
・家の中の空気量が少ないので換気しやすい
小さい家は狭いから、仮に湿気が解決できても我慢が必要と思われがちです。
でも、小さい家が狭いと感じるのは、壁の配置が悪いなどの心理的圧迫感なのです。
心理的圧迫感を取り除くために吹き抜けを作ると、抜け感が出て一気に家の中が広くなります。
冷暖房費に関しても、断熱材をしっかり入れることで問題なく抑えられます。
また、断熱材の量をしっかり入れても小さい家だから少なくて済みます。
心理的な圧迫感もなく、家の気密が行き届くことで、空気設計通りに換気がしやすい。
そうなると、小さい家は一気に快適になるのです。
結露やカビ、という面でも、小さい家は非常にオススメです。
換気がしっかりできる家は資産・投資価値も上がる
換気がしっかりできる家、というのは、気密、換気がしっかりしているということです。
これはつまり、家の性能そのものが高い、ということになります。
不動産投資や、家そのものの資産価値を考える時、不動産会社が見るのは家の性能面です。
断熱も含めるとさらに資産・投資価値が高まります。
家の空気が重い、湿気が多い、結露が多い、カビが生える。
そんな問題を根本から解決した家とは、資産・投資価値の上がった、快適な住まいになるのです。
Greener’s Houseは京都と滋賀で小さい家専門の家づくり中
家の空気が重い、息苦しい。
それってほとんどが換気がうまくできていません。
そして、換気がうまくできていない家の多くは結露が多く、カビも生えやすい状況になっています。
小さい家は特に換気しやすく、結露やカビの原因を根本から払拭することができるのでオススメしています。
ただ、小さい家と調べると、デメリットがずらり。
家が狭い。収納がない。空気がこもる。
でも、それは全て設計次第で解決できる問題なのです。
小さい家は宝の山。大きい家よりもむしろ快適になる。
にも関わらず、多くの現場を見にいくと、杜撰な工事が多くて小さい家の良さを活かしきれていません。
その結果、デメリットばかりが出てきてしまうのです。
だからこそ、僕達Greener’s Houseは小さい家を専門にしています。
小さい家を快適にするには、小さい家のための設計が必要。
でもそれさえできればはるかに住みやすい住まいになれる。
小さい家は宝の山。
小さい家? 最高やん!
その気持ちで、京都と滋賀で家づくりをしています。
施工事例や小さい家の設計や間取りについてはこちらをご覧ください。
まずは“空気のサイン”に気づくことから
|見えない結露は、あなたの感覚が先に教えてくれる
空気の異変には、身体の方が先に気づいている
- 布団がどことなく湿っぽい
- 押し入れを開けると、土のようなにおいがする
- 朝起きると喉が痛い
- 洗濯物に変なにおいが残る
こうした感覚は、ただの「気のせい」ではありません。
それは、空気に“何か”が混ざっているサイン。
そしてその原因のひとつが、壁の中で静かに進行している内部結露かもしれません。
“見えない湿気”に、どう気づくか
家の構造は目に見えない。
けれど、そこからにじみ出る異変は、暮らしの中にサインとして現れます。
- サッシまわりが常に湿っている
- 天井裏からカビ臭がする
- 壁紙が波打っている
- 押し入れの衣類ににおいが移っている
これらの“微細な違和感”を拾い上げていくことが、
空気と構造の破綻を防ぐための最初のステップです。
結露は、起きるべくして起きている。
でも、気づければ、止められる。
カビ臭も、素材の劣化も、家族の体調も──
すべては、空気が壊れ始めたサインだったのかもしれない。
構造は、変えられる。
空気は、整えられる。
そして暮らしは、もっと快適になれる。
僕達は営業メールや電話を一切しませんので、何かご質問などがあれば気軽にご連絡ください。
▶ 次に読む記事はこちら:
[「自然素材は湿気に強い?|無垢材・漆喰と“空気の相性”を見極める」]
Kindle書籍|深呼吸したくなる家はくらしをどうかえるのか。
なぜ僕は“空気”にこだわるのか?暮らしと温熱の思想を綴った一冊。
👉 Amazonで読む
無料PDF|工務店の頭の中~家づくりの本質は、価格の内側にある~
単価とは、“手の動き”と“素材への敬意”の積み重ねです。
この無料PDFは、価格ではなく、私たちの設計と施工の姿勢を伝えるために作りました。
「どの工程に、どんな技術と責任が含まれているか?」
それを知ったうえで、安心して見積もりと向き合っていただけたら嬉しいです。
👉 単価早見表PDFを今すぐダウンロード
note|現場の言葉と想いを、より深く綴っています
図面には載らない“暮らしの話”を、noteで語っています。
👉 noteを読む