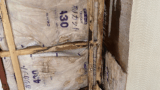引っ越せない。でも家を守りたい──その葛藤に答えます
「うち、親が住んでるし、引っ越すのは難しいんです…」
そんな声を、これまでたくさん聞いてきました。
京町家の耐震補強は、「住みながらなんて無理」
「全部空っぽにしないとできない」
と思われがちですが、それは半分だけ正解で、半分は誤解です。
耐震補強は、段階的に・部分的に行うことも可能です。
そして多くの場合、仮住まいに出なくても進められる方法があります。
この記事では、
「今の暮らしを守りながら、安全を手に入れる」──そのための方法と考え方を解説します。
なぜ「住みながらは無理」と思われているのか?
「耐震補強をするなら、住んでる人は仮の住まいを探さないと・・・」
そんなふうに聞かれることがあります。確かに、そう思ってしまうのも無理はありません。
なぜなら、多くの人が「耐震リフォーム=スケルトン改修(骨組みだけにする大工事)」というイメージを持っているからです。
よくある誤解①|全部の壁を壊す=全部住めなくなる?
確かに、家のすべてを一度空にして、柱から全面補強を行う「全解体型の補強工事」もあります。
ただ、それは**耐震性能だけでなく間取り変更や水まわり改修なども同時に行う“フルリノベ型”**の工事であって、
耐震補強そのものが常にスケルトン工事であるわけではありません。
よくある誤解②|工事中の音・ホコリ・安全面で生活できない?
もちろん、施工中に騒音や粉塵が出ることはありますが、
工事の内容・順序を設計すれば、生活動線を避けて施工することも可能です。
特に高齢のご家族がいる場合は、
・安全に生活を続けながら
・寝室を動かさずに
・順番に部屋ごと施工する
といった設計で進めることができます。
よくある誤解③|「大変そうだから…」で諦めてしまう
一番多いのはこのケースかもしれません。
「仮住まいの手配とか、大変そう」
「親の体調的に、環境を変えるのが怖い」
そう思って、必要性を感じていても踏み出せない方が多いのです。
でも実際には、「住みながら」の選択肢がちゃんとあるということを、まだ知らないだけ。
僕の読んで欲しい記事
家は家族の安全を守るものです。
何かが起きてからでは遅いのも現実として幾度となく目にしてきました。全てを完璧にする必要はありません。
部分的に補強していくという考えもあります。
住みながらでもできる理由──“段階施工”と“部分補強”の考え方
「じゃあ、実際にどんなふうに補強していくの?」
この章では、住みながらでも耐震補強を進められる理由と、具体的な工事の進め方をお伝えします。
耐震補強は“全体”でなく“部分”からできる
耐震工事というと、建物全体に大規模な補強を施すイメージがあるかもしれませんが、
実際には、地震の揺れに耐えるために重要な箇所を優先的に補強するという考え方が基本です。
例:
・1階の角の壁(耐力壁)
・接合部の金物補強
・土台や柱の根継ぎ
・基礎のひび割れ補修
これらを住んでいる部屋とは別の箇所から順番に行うことで、生活を保ちながら工事ができます。
工事の「順序設計」で生活動線を守る
在宅補強では、「どこから施工を始めるか」「どこを残しておくか」が非常に重要です。
- 寝室・水まわり・玄関など、生活の要所を“最後”に回す
- 作業動線と生活動線が重ならないように工事スケジュールを分割
- 家具を移動する場合も、一時的な仮置きや圧縮施工で回避可能
このように、工事工程そのものを生活と両立する前提で組み直すことが、在宅補強の鍵になります。
高齢の親と暮らしている家こそ「動かない設計」が求められる
仮住まいが難しい理由として一番多いのが、「親を移動させられない」という事情。
でもだからこそ、「住んでいる状態を前提に設計する」ことが、ほんとうのやさしさです。
次に読むべき記事
耐震診断、住宅のインスペクションは必ず行うようにしてください。
耐震リフォームは突発的にするものではありません。しっかりとした計画、今の住まいの健康状態を知って初めて実行できるものです。
実際に“住みながら補強した人”の声──「暮らしを壊さず、家を守れた」
「本当に住みながらできるの?」
そんな不安を抱えていた方が、実際に工事を終えてどう感じたのか。
ここでは、過去に在宅で耐震補強を行った方の事例をご紹介します。
事例①|80歳の母が暮らす実家を、仮住まいせずに補強(京都市 左京区)
- 【背景】老朽化した町家に高齢の母が一人暮らし。地震が来るたび不安に。
- 【工事内容】1階の耐力壁の補強、金物設置、柱根継ぎ、床下補強。
- 【対応】施工箇所を2分割し、昼間に1部屋ずつ交互に施工。寝室は最後まで手をつけず対応。
- 【施主の声】
「母を引っ越しさせずに済んだのが本当にありがたかった。
“いつも通りの生活”のまま、家を守れたことに心から安心しています。」
🏠 事例②|共働き夫婦+子ども2人、忙しい中でもリフォームを実現(京都市 中京区)
- 【背景】子育て中で引っ越しが現実的でない。耐震診断で不安箇所が判明。
- 【工事内容】接合部の補強、基礎の増設、構造用合板の追加。
- 【対応】生活エリアを3分割して週末ごとに分割施工。LDK→廊下→寝室の順に。
- 【施主の声】
「生活の場を壊さずに済んだことが一番大きいです。
“暮らしがそのまま続く安心”って、実は補強そのものよりも大事でした。」
安全を得ることと、暮らしを守ることは、どちらも大切にできる。
住みながらの補強は、“壊さない設計”そのものです。
「住みながらでもできる」──だから、未来を変えられる
今の住まいを残したい。
でも、生活は変えたくない。
そう思ったとき、かつては「どちらかを諦めるしかない」と言われていたかもしれません。
けれど、今は違います。
家を守るために、暮らしを壊す必要はありません。
暮らしに寄り添った設計ができる時代へ
在宅のまま耐震補強を進めるという選択肢は、
今の暮らしと、これからの安全を“両立”させるための方法です。
- 親を安心させたい
- 家族の負担を減らしたい
- 町家という「大切な場所」を、無理なく次世代につなぎたい
そうした想いを持つ人にこそ、「住みながら補強する」という考え方が、力になります。
未来に向けて、あなたにしかできない選択を
耐震補強は、家を強くするだけの工事ではありません。
それは、家族や自分自身の「これからの暮らし」を、
どう守っていくかという選択のプロセスです。
そしてその選択を、
「今の自分の暮らしを壊さない」というやさしさから始めることができる。
それが、住みながらの補強の真価です。こんな記事もよく読まれてます↓
僕のおすすめ記事NO2
まとめ
ここまで読んでくださったあなたは、
きっと「もしかしたら、うちもできるかもしれない」と、少し未来を想像しはじめているかもしれません。
でも、いきなり業者に連絡するのは怖い。
大きな工事になるのも不安。
だからこそ、まずはもっと小さくて、安心できる一歩から始めてみませんか?
- 「住みながら補強する」という選択は、もう特別なことではない
- 家族の暮らしを守りながら、安全を手に入れる設計が可能
- 小さな一歩からでも、その未来は動き出せる
あなたの想いを、直接聞かせてください
ご相談・ご質問など、小さなことでも大丈夫です。
👉 お問い合わせフォームへ

この記事おすすめの方
・見積もりを渡されてもどこをみたらいいのかわからない方
・お金をかけるべき場所、削っていい場所を自分で判断できるようになりたい方
この記事を読むとできるようになること
・見積もりの内訳を理解できる
・どこを削っていいか否かを自分で判断できる
・工務店の見積もりの根拠がわかる
無料、無登録で読める
見積もり読解ガイドのリンクはこちら↓