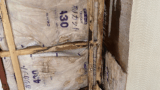「リノベーションって、いくらかかるんですか?」
京都で家づくりを検討する人から、必ず出る質問です。
工務店から見積もりを受け取っても、その数字が「高いのか安いのか」判断できず、不安になる方は多いものです。
さらに「最初は安いと思ったのに、追加費用で結局予算をオーバーした」という声も少なくありません。
リノベーションの価格は、相場を知らないと判断できず、工務店任せになってしまいます。
だからこそ大切なのは、相場を知り、価格が動くポイントを理解すること です。
「自分のリノベーション費用が妥当かどうか」を確認したい方は、こちらから資料をダウンロード
この記事では、京都のリノベーション価格をわかりやすく整理すること。
そして、費用が変動する具体的な要因を5つに絞って解説します。
京都でのリノベーション費用の相場とは?
まず押さえておきたいのが、リノベーションの大まかな価格帯です。
例えば70㎡前後の戸建てやマンションをスケルトンにして全面的に改修する「フルリノベーション」。
これになると、1200万〜1800万円程度 が一般的です。
一方で、キッチンや浴室など水回りだけを改修する「部分リフォーム」。
これだと、200万〜500万円 が目安になります。
ここにさらに断熱改修や気密強化といった「性能向上リノベーション」。
こちらを加えると、追加で300万〜800万円 が必要になることもあります。
つまり、「リノベーション」や「リフォーム」といっても、工事範囲や性能向上の有無で費用感は大きく変わるのです。
見積もりの内訳が不透明で不安な方はこちら 。
→リフォーム見積もりの落とし穴|契約前に知るべき5つの盲点
リノベーション価格を左右する5つの要因
次に、リノベーション費用がどのように変動するのかを5つの観点で整理します。
単語だけではわかりにくいので、具体例を交えながら説明します。
工事範囲
同じ「リビング改修」でも、壁紙を張り替えるだけなら費用は数十万円で済みます。
一方で、例えば、以下の工程を含めたとします。
・床材を無垢材に変える。
・断熱材を入れ直す。
・間取りを広げる。
こうなると、費用は一気に数百万円規模に膨らみます。
つまり「どこまで手を入れるか」が最初の分岐点です。
建物の構造
木造と鉄骨造、RC(鉄筋コンクリート)造では工事の難易度が違います。
木造なら比較的解体がしやすいのに対し、RCは配管や配線の変更にコストがかかりやすいです。
例えば、京都の町家のように伝統構造を残す必要がある建物。
こうなると、補強や職人技が必要になり、費用はさらに上がります。
性能向上リノベーション
断熱や気密改修を入れるかどうかで、費用は大きく変わります。
たとえば壁に断熱材を追加するだけでなく、サッシを高断熱窓に交換するとなると1箇所あたり数十万円。
ただしこれを省けば工事費は抑えられるものの、光熱費が上がり、住んでからのランニングコストで差が出ます。
性能向上リノベーションの費用感についてはこちら 。
→高断熱リフォームの費用と効果
使う素材
床を例にすると、一般的な合板フローリングなら1㎡あたり数千円。
これを無垢材にすると、1㎡で1〜2万円になることもあります。
素材の差は単なる「見た目」ではなく、空気の質感や耐久性に直結します。
水回りの位置
キッチンや浴室の場所を移動させると、配管工事が発生します。
「壁付けキッチンをアイランド型に変えたい」という希望はよくあります。
しかし、この場合、給排水管を延長する必要があり、工事費は一気に上がります。
また、ここで忘れてはいけないのが、家の見えない部分の劣化や耐震性能です。
こちらも一緒にご覧ください。
京都ならではの費用増ポイント
京都でのリノベーションには、地域特有の事情があります。
細長い「うなぎの寝床」敷地では、工事車両が入れず資材を手運びするケースも多く、その分工期や人件費がかさみます。
また、町家をリノベーションする場合は「外観や骨格を残す」ことが求められます。
そのため、補強や仕上げに職人技が加わるため、費用は通常より高くなります。
さらに「再建築不可」の物件では、建て替えができない分リノベーションしか選択肢がなく、長期的に住めるよう性能向上を組み込む必要があります。
これも初期費用を押し上げる要因となります。
僕達は鰻の寝床のような形の物件や、小さい物件を専門にしています。
小さい家って実は高性能な住宅に最適で、メリットがたくさんあります。
メリットや他社との違いなどを載せているので、気になった方はぜひご覧ください。
見積もりの中身を読み解く
見積もりを見る時の注意点
最後に、多くの人が見落としがちな「見積もりの読み方」について。
見積もりの金額だけを見ても、その根拠がわからなければ意味がありません。
例えば、
「仕様」とは「どの範囲を工事するか」。
「グレード」とは「どんな設備や素材を選ぶか」を指しています。
同じ「キッチン交換」でも、標準仕様のシステムキッチンなら80万円前後、ハイグレードモデルを選べば150万円以上になります。
つまり「仕様やグレードの違い」は、費用に直結する具体的な差なのです。
また「諸経費」や「仮設工事費」といった見積項目も注意が必要です。
これらが抜けている見積もりは、あとで追加請求が発生する可能性が高いのです。
僕達が提供するのは、リノベーション後の快適な暮らし
リノベーションをするとしても、僕達はあくまでプロとして、不必要な部分は「本当にしますか?」とお話しします。
同時に、お客様が不必要だと思っているところでも、その後の暮らしを考えた時に「ここがないときっと後で後悔するかもしれない」と思った場合は、必ず伝えるようにしています。
というのも、業者はプロだと思っていて任せていたら、案外不必要なところまでリノベーションしていたり、プロ目線から使いづらいと思われることがあれば教えて欲しかったという声は多いのです。
だからこそ、本当に必要な部分と、不必要な部分、希望や要望を照らし合わせるようにしています。これによって、本当に快適な暮らしができつつ、自身の理想が反映された住まいにリノベーションができるのです。
リノベーションが終わったら、そこから暮らしが始まります。
僕達が本当に大切にしたいのは、リノベーションをした後の快適な暮らしです。リノベーションをしてよかった。快適な暮らしができるようになった。そう言ってもらえるように、住まう人の暮らし方に合わせて、特に小さい家を専門に、リノベーションやリフォームを行っています。
暮らしやすさはもちろん、家の性能を高めること、家の資産・投資価値を高めることなどを大切にしています。小さい家は実はとても暮らしやすくて、快適にできる。小さい家が暮らしづらいのは設計力不足。
そんな僕達についての詳細はこちらをご覧ください↓
まとめ|正しい理解が後悔を防ぐ
リノベーション費用は「高いか安いか」ではなく、どこに投資しているか で判断すべきものです。
- 相場を知ることで冷静に判断できる
- 費用を左右する5つの要因を理解する
- 京都特有の事情を見落とさない
- 見積もりの中身を比較できるようになる
この視点を持てば、「予算オーバーで後悔する」リスクを大きく減らせます。
リノベーション費用は「提示された金額」そのものではなく、中身の理解 がすべてです。
仕様やグレード、性能改修の有無を整理しないまま契約すれば、後から追加費用が膨らみ、暮らしの質も犠牲になります。
僕たちはすべての相談で 「工事範囲」「性能」「素材」をセットにした費用プラン を作成し、どこにいくらかかっているかを数字で見える化しています。
👉 もし今見積もりを手にして「高いのか安いのかわからない」と感じているなら、一度ご相談ください。
京都のリノベーション相場を基準にしながら、必要な投資と不要な費用を仕分け、納得できる計画をご提案します。