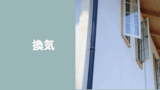なぜ京都の家づくりに“空気の設計”が必要なのか
僕が「断熱・気密・換気は、セットで考えましょう」と話すと、
「京都でもそこまでやる必要あるんですか?」って聞かれることがよくあります。
でも、こう答えています。
「むしろ京都だからこそ、空気の設計が必要なんです。」
なぜなら、京都という土地には、独特の気候と住宅のクセがあるからです。
京都の家は、寒くて、湿気がこもる
冬になると底冷えし、夏は湿気がまとわりつく。
しかも町家や古い木造住宅では、断熱も気密も、ほとんどないに等しい状態の家も多いです。
その結果──
- どれだけ暖房しても、足元が冷たい
- 窓まわりや押入れにカビが出る
- 家の中で“空気の重たさ”を感じる
これ、たまたまじゃないんです。
気密も換気も整っていない中で断熱だけ強化しても、快適にはならない。
空気の設計とは、“気持ちいい”を科学すること
断熱=熱を逃がさない
気密=空気をコントロールする
換気=空気を入れ替える
この3つが揃って、ようやく**“住まいの空気”が設計される**んです。
- 結露が出にくくなる
- 空気が軽くなる
- 部屋の温度が安定する
- 花粉やPM2.5をシャットアウトできる
つまり、“深呼吸したくなる家”は、感覚だけじゃなく設計と施工でつくられるものなんですよ。
第2章|断熱は“素材”じゃなく“戦略”で考える
「断熱材って、何を使うのが一番いいんですか?」
リノベーションの打ち合わせでよく聞かれる質問です。
でも僕はいつもこう返します。
「断熱材は、“何を使うか”より、“どう納めるか”がすべてです。」
京都の断熱に必要なのは「現実対応力」
京都は寒さが厳しいけれど、北海道みたいな基礎断熱は過剰。
しかも町家や築50年超の木造住宅では、断熱材を入れるスペース自体が制限されるケースもあります。
だから僕たちは、高性能グラスウール+気密シート施工を基本にしています。
- 柔軟に納まる
- 厚みで性能調整できる
- 施工性とコストのバランスが良い
- リノベ現場で“失敗しづらい”
素材のスペックじゃなく、現場の状況と暮らしに合わせて戦略を立てる。
それが、京都での断熱設計の本質です。
結露やカビとセットで考えるのが「断熱」
断熱材は「暖かさ」だけを生むものじゃありません。
使い方を間違えると、壁の中に湿気がたまって結露を起こし、カビや腐朽菌の原因になる。
とくに京都のように湿気が多く、冬も乾燥しすぎない地域では、
- 防湿層(気密シート)の有無
- 通気層の設計
- 既存壁との相性
──こういった要素もすべて断熱とワンセットで考える必要があるんです。
断熱は「未来の暮らし方への投資」
断熱を強化することは、快適性だけじゃなく、将来の健康・家計・資産価値にも影響します。
- ヒートショックリスクの低減
- 電気代の安定
- 売却時に省エネ性能が評価される
つまり、断熱は“今の我慢”を解消するだけじゃなく、これからの暮らし方に芯を通すものなんです。
断熱って、ただの材料選びじゃなくて、
家全体と住む人を見つめて戦略を組む設計行為なんです。
こちらの記事も読まれてます↓
第3章|気密=空気を整えるための静かな技術
気密って、なんとなく「寒冷地向けの特殊な施工」というイメージが強いかもしれません。
でも、僕はむしろ京都のような中途半端に寒くて湿気もある地域こそ、気密が必要だと感じています。
それは、“閉じ込めるため”じゃなくて、空気を整えるためなんです。
断熱だけじゃ足りない、体感がついてこない理由
「断熱材を入れたのに寒いままです」
「暖房しても床だけ冷たいんです」
そう相談されたとき、僕がまず見るのはすき間。
つまり気密が取れているかどうか。
暖めた空気がすき間から逃げて、外の冷気が入ってきたら──
断熱材のスペックは意味を失います。
気密施工の本質は、“空気の流れをデザインすること”
- サッシまわりにすき間がないか?
- 壁と天井のつなぎ目に気流が抜けていないか?
- 電気配線や配管周りが未処理じゃないか?
こういった細かい施工の積み重ねが、**「静かで、温度のムラが少なく、空気が澄んだ空間」**をつくるんです。
「気密が取れている家」は、体がリラックスする
- 足元だけ寒い
- 冷たい風が首筋に当たる
- 暖房をつけてもすぐ冷める
これ、全部“気密が甘い”ことによる体感なんです。
逆に、気密がしっかり取れている家は、エアコンの設定温度が1〜2℃低くても快適に感じます。
しかも、空気の音がやわらかくなって、「静かで包まれてる感じ」が生まれる。
これは僕自身、初めて高気密住宅に入ったときに強く感じたことです。
僕たちが届けたいのは、「性能値」じゃなく「深呼吸できる空間」
もちろん、C値(気密性能の数値)も大事です。
でも僕はそれ以上に、「空気の質が暮らしをどう変えるか」に興味があります。
- 匂いがこもらない
- 花粉が入りにくい
- エアコンを切ってもほんのり暖かい
こういう**“じんわり効く快適さ”を支える静かな技術**が、気密なんです。
第4章|換気は、住まいと健康をつなぐインフラ
「24時間換気はついてるけど、効いてる実感がない」
そんな声をよく聞きます。
でも、それも当然かもしれません。
換気って、“設置しただけ”では機能しないんです。
空気は見えない。だからこそ、どこから入って、どこを通って、どこへ抜けていくのか。
その流れまで設計されていなければ、ただのファンに過ぎません。
空気が動かない家は、人をじわじわ疲れさせる
- 朝起きてもだるい
- なんとなく頭が重い
- 子どもが集中できない
- カビや結露が出やすい
これらの原因が「空気のよどみ」にあることは、意外と知られていません。
室内で呼吸すれば、CO₂は増える。湿気も溜まる。匂いもこもる。
それが巡らない空気として蓄積していくと、知らず知らずのうちに人を消耗させるんです。
設計された“空気の流れ”が、暮らしを変える
僕たちが大切にしているのは、ただ排気する・給気するだけじゃなく、空気の経路そのものを設計すること。
- どこで新鮮な空気を取り入れるか
- どこで汚れた空気を出すか
- どの部屋をどう通り抜けるか
- 冷気が直接当たらない工夫があるか
これが設計できていると、家の中にゆるやかな呼吸のような流れが生まれます。
結露、カビ、アレルギー──空気が原因になる時代
換気がうまくいっていない家でよく起こるのが、壁や天井裏の見えない結露。
そこからカビが発生し、空気中に胞子が舞う。
それを毎日吸っていると、アレルギーや喘息、慢性的な不調の原因になる。
花粉やPM2.5だけじゃなく、「家そのもの」が空気を汚す構造になってしまうんです。
“空気の家事”ができる家にする
料理や洗濯と同じように、空気も“整える”必要がある。
でもそれは、住む人がやるのではなく、**設計と施工が担うべき「見えない家事」**だと僕は思っています。
空気の質が整っていれば、住む人はただ“呼吸するだけで、整う”。
そのためのインフラとして、換気は最も静かで、最も力強い存在なんです。
こちらの記事は人気です。自然素材の家って本当は?
第5章|結論:空気を設計するという考え方
僕が家づくりで一番大切にしているのは、**「空気の質をどう設計するか」**ということ。
目に見えないけれど、確実に人の心と体に影響を与える空気。
その空気をどうつくるかを、建築の言葉で考えていくことが、
これからの“暮らしを整える家づくり”だと思っています。
素材でも、間取りでもない。「空気」が暮らしの質を決める
無垢材を選ぶのも、自然素材を取り入れるのも素敵なこと。
でも、それ以上に僕が大事にしたいのは、その素材たちが呼吸できる空気の流れがあるかどうか。
- 温度だけでなく、空気が軽いか
- 湿度がこもらないか
- 空気がスムーズに出入りしているか
そういう“見えない要素”こそ、暮らしの快適さの根っこになるんです。
「断熱・気密・換気」は、図面では見えないけれど
家のプランを見ても、そこに断熱や気密や換気の仕組みは描かれていないかもしれない。
でも、見えないからこそ、考える力が必要です。
- なぜここに断熱を入れるのか?
- なぜこのラインで気密を取るのか?
- なぜこの場所に給気口を設けるのか?
そういう**“なぜ”の連続**が、空気を設計するということ。
僕たちが届けたいのは、「数値」ではなく「深呼吸」
C値やUA値、換気量といった性能値はもちろん大切。
でも、その先にあるのは、
「ただの快適」じゃなく、「心まで整う空気」を届けることだと思っています。
朝起きたときに、「今日も空気が気持ちいいな」って思える。
子どもが走り回っても、体が軽く感じる。
そんな家を、「空気から」つくることが、僕たちの家づくりです。
まとめ|深呼吸したくなる家は、空気からつくられる
断熱だけじゃ足りない。
気密だけでも片手落ち。
換気があっても、それが空回りしていたら意味がない。
3つが揃って、初めて空気が整う。
そして、整った空気が、人の体と心を包み込んでくれる。
それが、僕たちが届けたい「深呼吸したくなる家」の正体です。
この記事は必ずお読みください。
お問合せはこちら|あなたの想いを、直接聞かせてください
ご相談・ご質問など、小さなことでも大丈夫です。
👉 お問い合わせフォームへ
Kindle書籍|深呼吸したくなる家はくらしをどうかえるのか。
なぜ僕は“空気”にこだわるのか?暮らしと温熱の思想を綴った一冊。
👉 Amazonで読む
無料PDF|工務店の頭の中~家づくりの本質は、価格の内側にある~
単価とは、“手の動き”と“素材への敬意”の積み重ねです。
この無料PDFは、価格ではなく、私たちの設計と施工の姿勢を伝えるために作りました。
「どの工程に、どんな技術と責任が含まれているか?」
それを知ったうえで、安心して見積もりと向き合っていただけたら嬉しいです。
👉 単価早見表PDFを今すぐダウンロード
note|現場の言葉と想いを、より深く綴っています
図面には載らない“暮らしの話”を、noteで語っています。
👉 noteを読む