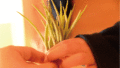「いいな」と思っていた漆喰の家に、不安を感じてしまったあなたへ
自然素材の家って、なんだか心が落ち着きますよね。
特に、漆喰の白い壁は、光をふんわりと受け止めて、空間がやわらかく感じられる——そんな美しさに惹かれている方も多いと思います。
でも、その一方で、こんな気持ちがよぎることもありませんか?
- 「すぐ汚れたり、傷ついたりするんじゃないか」
- 「お手入れが大変そう」
- 「家族の暮らしに合わなかったらどうしよう」
そうなんです。
見た目のやさしさや自然な素材感に惹かれても、「本当に自分に合っているのか?」という不安は、誰の中にもあるものなんですよね。
僕たちのもとにも、そんなふうに迷いながらご相談に来てくださる方がたくさんいます。
そして僕はいつも思うのです。
「その迷いは、すごく自然で、大切にしてほしい気持ちだ」と。
だからこの記事では、「漆喰の家でよくある“不安”」と、その一つひとつにどんな向き合い方ができるかを、できる限り丁寧にお話していきます。
押しつけではなく、
宣伝でもなく、
ただ、これからの家づくりを考えるあなたにとって、少しでも安心材料が増えるように。
そんな気持ちで、言葉を重ねていきますね。
「漆喰は体にやさしい」は本当?──実は“扱い方”にコツがある素材です
自然素材=体にやさしい、というイメージはとても強いですよね。
実際、漆喰は化学物質をほとんど含まず、室内の空気を整えてくれる優れた素材です。
でも、だからといって「誰にとっても絶対に安全」というわけではありません。
アルカリ成分による刺激に注意が必要です
漆喰には強いアルカリ性があります。これはカビの発生を抑えたり、消臭効果を発揮するうえでの長所でもありますが、一方で…
- 施工中に素手で触れると、肌が荒れたりヒリつきを感じることがある
- 乾燥前の粉末が舞い、目や喉に刺激を感じるケースもある
- 特に、小さなお子さんや敏感肌の方は、触れる場所に使う際に注意が必要
こうした声は実際に漆喰の家に住むご家族からも聞かれます。
「塗ったばかりの頃、子どもが手で触ってしまって、手の甲が赤くなってしまった」
そんな体験談を聞いたこともあります。自然素材とはいえ、扱い方にはコツが必要なんですね。
落ち着けば“空気のフィルター”になる
ただし、乾燥が進むとアルカリ性は徐々に落ち着き、
漆喰はとても優れた調湿・抗菌素材へと変わっていきます。
乾燥後は——
- 室内のにおいや湿気を吸着する
- カビやウイルスの繁殖を抑える
- 呼吸するように空気を整える
こうした“空気のフィルター”のような存在になります。
だからこそ、施工前後の注意をきちんと理解しておくことが大切。
“素手で触れない”“乾燥中は換気をする”など、ちょっとした配慮で安全性は格段に高まります。
小さな補修は「チョーク」で簡単に
また、漆喰の壁に小さな傷や欠けができたときは、
白いチョークで擦って馴染ませるだけでも補修可能です。
傷が目立ちにくいのも、漆喰ならではのメリット。
大がかりな工事をしなくても、日々のケアで“育てる感覚”が味わえる素材なんです。
このように、漆喰は「体にやさしい」だけでなく、**“付き合い方に少し知恵が要る素材”**です。
でもその一手間が、家と暮らしへの愛着に変わっていく——
そんな素材だと、僕は思っています。
「自然素材は大変そう…」の不安と、“それでも選んだ理由”
「漆喰や無垢材って手がかかりそう」
「メンテナンスとか、失敗したらどうしよう」
そんなふうに迷う声は、本当にたくさん聞いてきました。
でも実際に自然素材の家に暮らしている人たちは、
驚くほど多くの方が「選んでよかった」と話してくれます。
今回は、いくつかのリアルな暮らしの声をご紹介しながら、
“自然素材を選ぶときに知っておきたいこと”を見ていきます。
事例①|「杉の床が傷だらけ。でも、それが“暮らしの地図”になった」
あるご夫婦が杉の無垢床を選んだとき、最初に気にしていたのは「傷がつきやすいんですよね?」という点でした。
実際、小さなお子さんがいる家庭では、積み木やおもちゃであっという間に跡がつきます。
でも、その後にご主人がこう言ったんです。
「あの傷、見てると“ああ、この頃はこれで遊んでたな”って思い出すんです。地図みたいですよ、うちの暮らしの」
この言葉が、とても印象に残っています。
“味わい”という言葉では語りきれない、暮らしそのものへの愛着がそこにありました。
事例②|「漆喰の壁、手垢も子どもの成長記録に」
漆喰の壁に、うっすらと手の跡が残ることがあります。
特に階段や出入り口など、よく触れる場所には少しずつ汚れがついてきます。
でも、あるお母さんはこう笑って話してくれました。
「これは、子どもがよじ登ってたときの跡なんです。まだこんなに小さかったんだなぁって…ちょっと嬉しくなるんです」
もちろん、気になる場合は部分的に補修することもできます。
でも、汚れを“汚れ”と捉えるか、“記憶”と捉えるかで、家との関係は変わるのだと思います。
事例③|「香りが合わなかった。でも、ちゃんと変えてくれて安心した」
自然素材には、香りの個性があります。
特に桧や杉の香りにはフィトンチッドと呼ばれる成分があり、リラックス効果が期待される一方、体質によっては強く感じすぎることもあります。
過去に、こんな相談がありました。
「檜の香りが強すぎて、数日住んだだけで頭が重くなってしまったんです…」
僕たちはすぐに素材を杉材に変更。
その後は快適に暮らせるようになったと聞いて、ホッとしたのを覚えています。
**自然素材=絶対安心ではなく、「相性がある」**というのが正直なところ。
だからこそ、施工前にしっかり触れて、体で感じて、確かめることが何より大切です。
事例④|「お手入れは面倒?いいえ、“育ててる感じ”があるんです」
「自然素材ってメンテナンスが大変そう」
これもよく聞かれます。でも実際には——
「思ったより全然簡単でしたよ。むしろ、愛着が湧くんです」
という声が多いんです。
- 無垢の床は数年に1度ワックスをかけるだけ
- 傷がついても、濡れタオルとアイロンで簡単に膨らませて補修可能
- 壁の欠けはチョークを擦りつけて補修できる
そうやって、**手をかけるたびに“育っていく家”**になるのが、自然素材の魅力なんです。
「後悔しない素材選び」とは、“正しさ”より“納得”を選ぶこと
自然素材の家には、完璧さはありません。
手もかかるし、合わないこともあるかもしれない。
でもそれを理解し、受け入れたうえで「それでもこれがいい」と思えたとき——
住まい手は、「後悔」ではなく「納得」の中に暮らすことができます。
僕はそんな、“納得して選んだ家”を一緒に考えられる存在でありたい。
次章では、漆喰の家がなぜ“心地よく感じる”のかについて、もう少し深く掘り下げてみたいと思います。
僕のおすすめ記事
珪藻土も漆喰と同じように室内壁の塗り材としては人気が高いです。
ですが、珪藻土も施工者がしっかりとした知識がないとカビの原因につながります。
お時間がゆるすならこの記事もぜひ読んでください。
漆喰の家が「気持ちいい」と言われる理由──それは“素材と空気”の関係にあった
「なんだか、空気がきれいな気がする」
漆喰の家を訪れた人が、よく口にする感想です。
でもそれは、気のせいじゃありません。
漆喰には、目に見えない空気の質を整える力があるんです。
漆喰は“空気を吸って、吐く”素材
漆喰は「調湿性」と呼ばれる性質を持っています。
- 湿度が高いと、空気中の水分を吸い込み
- 乾燥してくると、ゆっくり吐き出す
つまり、部屋の湿度を自動で整えてくれる壁のような存在です。
京都のように夏は蒸し暑く、冬は底冷えする地域では、この働きがとても大きい。
季節による湿気のムラを、漆喰が自然と“調律”してくれるからです。
でも、漆喰だけでは快適にはならない
とはいえ——
漆喰を塗っただけでは、家全体が快適になるわけではありません。
大事なのは、空気が家の中をめぐっているかどうかです。
例えば、
- 換気が悪ければ、湿気はどこかにたまる
- 気密が甘ければ、冬に冷たい隙間風が入る
- 断熱が不十分なら、漆喰が湿気を吸っても乾かない
そんな状態では、せっかくの漆喰の力も発揮できません。
漆喰の家に「心地よさ」を感じるのは、
空気の流れと素材の呼吸が共鳴している家だけなんです。
「漆喰は匂いを吸う」って本当?
はい、本当です。
漆喰には、においの原因物質を分解・中和する働きもあります。
例えば:
- 焼き魚や揚げ物のにおいが残りにくい
- ペットのにおいがこもりにくい
- トイレや脱衣所など、水まわりのにおいも軽減
つまり、家の中の空気がすっきりと整うということ。
これも、「なんとなく居心地がいい」と感じる理由のひとつです。
漆喰の力を引き出す“設計”とは?
僕たちは、漆喰をただ塗るだけでなく、
**「漆喰が呼吸できる空間をつくること」**を大切にしています。
たとえば:
- 外気との温度差が激しくなる場所には、断熱+換気で結露を防ぐ
- 水まわりには“乾きやすい動線”を設計し、湿気をためない
- 壁の一面だけでなく、家の“呼吸する面積”を増やす
こうすることで、漆喰が持つ調湿・脱臭効果は最大限に活きてくるのです。
「漆喰の家が気持ちいい」のには、理由がある
それは——
- 漆喰が空気中の湿気やにおいを整えてくれること
- その力を活かす“空気設計”がされていること
- 京都のような気候でも、心地よく暮らせる仕組みがあること
漆喰の家に「癒やされる」「落ち着く」と感じるのは、
単に自然素材だからではなく、素材と空気が“うまく呼吸している”からなんです。
漆喰で後悔しないために──選ぶ前に知っておきたい3つのポイント
漆喰の家に憧れている。
でも、どんなことに注意すればいいのか分からない——。
そんな方に向けて、
**後悔しないために押さえておきたい“3つの視点”**をまとめました。
① 肌や体質に合うか、事前に確かめておく
漆喰は天然素材ではありますが、強アルカリ性です。
これが調湿・防カビ・消臭といった優れた効果の源でもあるのですが、
一部の人には肌荒れや刺激を引き起こす場合があります。
特に:
- 小さなお子さんがいるご家庭
- アレルギーや敏感肌の方
- 手で触れることが多い場所(階段手すり横や玄関まわり)を漆喰にする場合
こうした場合は、施工前に必ずサンプルに触れてみることをおすすめします。
② 補修は“チョーク1本”でできる
「漆喰って、傷ついたらどうするの?」という声もよく聞きます。
実は、軽い傷ならチョークを塗り込むだけで補修できるんです。
手順は簡単。
- 白いチョークを削る(手でもOK)
- 指でこすりながら、傷部分にすり込む
- 最後に軽く乾拭きする
これだけで、小さなひびや汚れは驚くほど目立たなくなります。
だからこそ、「育てる素材」として暮らしに馴染んでいくんです。
③ “合わない人”がいることも、正直に伝えたい
僕たちがこれまでご一緒した中で、ごくまれにですが
「漆喰のにおいや感触がどうしても合わなかった」という声もありました。
たとえば:
- においが強く感じられて、頭が重くなる
- 粉っぽさに敏感で、喉がイガイガする
- 表面のざらつきが苦手で、日常的に気になる
自然素材=誰にでも優しい、ではありません。
“自分に合う素材かどうか”を確かめてから選ぶことが、なにより大切です。
まとめ|“漆喰を選ぶこと”は、“自分にとっての心地よさ”を選ぶこと
漆喰にはたしかに魅力があります。
でも、それは「みんなにとって正解な素材」だからではありません。
大切なのは——
- 素材の特徴をちゃんと知ること
- 自分の暮らしに合うかどうかを確かめること
- 「育てながら住む家」を楽しめるかどうか、ということ
漆喰の家を選ぶというのは、
“住む人自身の心地よさ”と丁寧に向き合う選択なんです。
“漆喰の家”を長く、心地よく保つための5つのヒント
漆喰は「塗ったら終わり」の素材ではありません。
呼吸し続ける壁だからこそ、暮らし方ひとつで、家の空気が変わります。
ここでは、漆喰と長く、心地よく付き合うためのヒントを5つご紹介します。
1. 定期的に“空気の通り道”をつくる
漆喰は調湿機能がありますが、空気が停滞してしまうと性能が十分に発揮されません。
定期的に窓を開けて空気を通し、湿気やにおいをためこまない習慣をつけましょう。
京都のような湿気の多い地域では、特に**「朝と夕方の換気」**を心がけるだけでも効果があります。
2. 壁に直接モノを当てない
漆喰の壁は柔らかく、手や家具が当たると跡がつきやすくなります。
可能であれば家具と壁の間に2〜3cmの隙間をつくり、
湿気のこもりや、チョーク補修の頻度を抑えましょう。
3. 汚れは“こすらない”、落ち着いて対処
うっかり手垢や黒ずみがついてしまっても、慌ててゴシゴシこすらないように。
軽い汚れは消しゴムやチョーク、重曹ペーストで優しく拭くのがコツ。
漆喰は「塗り重ねて育てる」素材でもあるので、
経年による風合いを楽しみながら、“きれいにしすぎない”暮らしもひとつの選択です。
4. 加湿器の置き場所に注意
冬場に加湿器を使う場合、漆喰の壁の近くに置くと結露や膨れの原因になります。
できるだけ部屋の中央、かつ壁から離れた場所に設置しましょう。
自然素材の家は「湿度のコントロール」がとても大切です。
5. 傷や割れは“味”になると考える
漆喰は完璧ではありません。
でも、完璧じゃないからこそ愛おしい素材です。
ひびや割れ、小さな傷は、その家で暮らした証拠でもあります。
無理に直さず、**「家と一緒に年を重ねていく」**という感覚を持てたら、
その家は“自分の居場所”として深く根を下ろしはじめます。
漆喰の家を選ぶことは、ただ“自然素材を取り入れる”ということではありません。
それは、素材と暮らしのリズムを共にする選択。
あなたの手と、時間と、空気がつくる——
世界にひとつだけの“呼吸する家”。
その一歩を、僕たちはそっと背中から支えられる存在でありたいと思っています。
あなたの悩みを聞かせてください(しつこい営業メールなどは一切お送りしません)
ご相談・ご質問など、小さなことでも大丈夫です。
👉 お問い合わせフォームへ

この記事おすすめの方
・見積もりを渡されてもどこをみたらいいのかわからない方
・お金をかけるべき場所、削っていい場所を自分で判断できるようになりたい方
この記事を読むとできるようになること
・見積もりの内訳を理解できる
・どこを削っていいか否かを自分で判断できる
・工務店の見積もりの根拠がわかる
無料、無登録で読める
見積もり読解ガイドのリンクはこちら↓