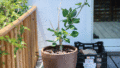「うちは24時間換気がついてるから安心です」
そうおっしゃる方は多いのですが、実際に機能していない家が想像以上に多いんです。
僕はこれまで数多くの中古住宅やマンションをリノベーションしてきましたが、
その中で「換気しているつもりなのに、空気がよどんでいる家」を何件も見てきました。
“あるある”な換気の落とし穴
24時間換気は法律で義務化されているものの、設計と運用が適切でなければまったく効果が出ません。
たとえばこんなケース:
- 給気口のフィルターがホコリで目詰まり
- 家具で給気口がふさがれている
- 排気口の風量が弱すぎて空気が動かない
- 廊下やクローゼット内の空気が常にこもっている
- そもそもの換気容量などが全く計算されていない
- 気密施工の不備で計画的な換気になっていない
これでは、せっかく換気設備をつけていても、空気の流れが“断ち切られている”んです。
■ 施主の声:京都・Y様 木造築32年
「窓を開けていないとニオイがこもるなと思っていたんですが、換気容量が小さかったようです。換気している“つもり”だったんです」
このように、24時間換気は“設置しただけ”では意味がないということを、多くの方が知りません。
空気の通り道は、設計でつくる
僕たちキノスミカが家づくりやリノベーションで重視しているのは、
換気設備だけに頼らない「空気の流れそのものを設計する」という考え方です。
具体的には、
- 給気→排気のルートが建物全体に循環するような間取り
- 空気が滞りやすい場所(トイレ、洗面、収納)に排気口を設ける
- 空気が壁や天井裏で迷子にならないよう、気流の出口をコントロール
- 断熱気密の再考
つまり、設備ではなく「空気の動線」を作り、読むことが最も重要なんです。
自然素材×空気設計で空気が変わる
無垢材や珪藻土といった自然素材も、確かに空気に良い影響を与えます。
でも、それも空気が滞らない環境でこそ意味がある。
たとえば、湿気を吸うはずの杉の床も、空気が停滞していればカビの温床になります。
僕たちは、まず“空気が動く家”をつくり、その上で自然素材を活かすことを徹底しています。
リノベでも換気は改善できる
「古い家だから、どうせ換気はあきらめるしか…」
そんなふうに思っている方にこそ伝えたい。
換気の経路は後からでも設計し直せます。
実際に、築35年の家を断熱リノベする際に、
既存の換気設備は残しつつ、ルートを読み直し、空気の流れがまったく違う家に生まれ変わった事例もあります。
暮らしの質は、「呼吸のしやすさ」で決まる
「風通しの良い家」は、気持ちまで軽くしてくれる。
見た目のデザインや性能の数値以上に、空気の質が“暮らしの快適さ”を左右すると、僕は確信しています。
だからこそ、換気を“つけたら終わり”にせず、
家全体を呼吸させる設計を、僕たちはこれからも伝えていきたい。
もっと知りたい方はこちらから
👉 無料相談してみる